カテゴリー: 国際相続サポート

国際相続サポート
海外移住で相続税は避けられる?10年ルールの真実と今後の改正動向
「海外に移住すれば相続税を払わなくて済む」と耳にしたことがある方もいるでしょう。 実際に日本の相続税では、「被相続人及び相続人が10年超海外に住んでいると、一部の財産を除いて日本の相続税が課されない」というルールがあります。 このルールを「10年ルール」といいます。 しかし、実際には国内に残した不動産や預金は課税されますし、今後の税制改正も大きく影響します。 この記事では「10年ルール」の基本と注意点、海外移住で本当に相続税が避けられるのか、さらに今後の税制改正の可能性までわかりやすく解説します。 第1章 相続税の「10年ルール」の3つのポイント 結論からいうと「10年ルール」により相続税を回避するためには以下の3つのポイントを満たす必要があります。 この章ではその3つのポイントについて解説します。 1-1 相続開始前10年超海外に居住している 「10年ルール」により相続税を回避するには、相続開始前10年を超えて日本に住所がないことが要件になります。 なお、日本に住所があるかないかの判定は個別に判断をすることになります。 例えば、日本と海外を行き来している場合には、実質的な生活の拠点が日本にあるのか海外にあるのかを判断し判定をします。 つまり、見かけではなく実態として日本に生活の拠点があると考えられた場合には日本に住所があるものとして課税がされることになります。 1-2 被相続人だけでなく相続人も海外に移住している 「10年ルール」により相続税を回避するには、被相続人(亡くなった人)と相続人(財産を受け取る人)の両方が海外に相続開始前10年を超えて住んでいたことが要件になります。 (相続人が外国籍の場合は相続人が海外に10年を超えて住んでいた要件は必要ありません) 例えば被相続人(父)が相続開始前10年超海外に住んでいたとしても、相続人(子)が日本に住んでいた場合は、原則日本国内にある財産にも海外に所在している財産にも日本の相続税が課されることになります。 つまり、国外移住により日本の相続税を回避するためには相続人も含め家族全員で海外に移住する必要があります。 1-3 財産も全て日本国外にある 「10年ルール」により相続税を完全に回避するには、財産も全て国外に持ち出す必要があります。 例えば、国内の不動産・銀行預金・日本企業の株式(日本の証券会社でなどは、移住の有無にかかわらず相続税の対象となります。 なぜなら、どんな場合でも、日本国内の財産は日本の相続税の課税対象となるからです。 つまり、海外移住により完全に相続税を回避するためには、財産も全て国外に持ち出す必要があります。 ただし、有価証券を海外に持ち出す場合には「国外転出時課税」の適用を受ける可能性があるので注意が必要です。 1-4 フローチャート 海外移住した後に相続が発生した場合に日本の相続税が課されるかどうか」をフローチャートにまとめると次のようになります。 第2章 海外移住だけで相続税回避は難しい では、この「10年ルール」を使い容易に日本の相続税は完全に回避することができるかというと、現実には難しいです。 この章ではその理由を簡潔に記載します。 2-1 「10年を超える居住」だけでは完全に相続税回避はできない 海外移住だけで完全に相続税が回避できるかというと、当てはまらない場合があります。 例えば、日本に財産を残している場合です。 確かに「相続開始前10年を超えて海外に住んでいれば、国外財産には相続税がかからない」というルールは存在します。 しかし、前述したようにこれは「国外財産」に限定される話であり、日本国内に残した財産には相続税が課税されます。 【事例】 母がフランスに12年間住んで亡くなりました。 相続人である娘もフランスに母と同じ12年間フランスに住んでいます。 財産がフランスの銀行預金:5000万円と東京のマンション:8000万円だったとします。 フランスの銀行預金(国外財産):日本の相続税はかかりません。 東京のマンション(国内財産):相続税が課税されます。 このように、海外移住をしても「日本に財産を残している限り、相続税ゼロ」にはならないのです。 2-2 帰国後に亡くなった場合、実質上の居住地の問題、税制改正により相続税が回避できない場合がある 「10年ルール」を満たそうと海外移住しても安心ではなく、相続税が回避できない場合があります。 それぞれのリスクをまずは認識しておくことが重要です。 ・帰国リスク 父が海外に11年住んだ後に帰国し、その数年後に亡くなった場合を考えてみましょう。 この場合、日本に住所があるとみなされ、国外財産も相続税の課税対象となる可能性があります。 つまり「一度帰国したらリセットされる」というイメージです。 ただし、帰国前に10年ルールを満たした状態で財産を贈与した場合には、日本の贈与税は課税されません(もっとも、移住先の国で贈与税等が課される可能性はありますのでご注意ください)。 また、帰国後に亡くなった場合であっても、すでに贈与済みの財産については相続税の課税対象にはなりません。 ・居住地リスク 完全に帰国をしていなくても、頻繁に日本に一時帰国している場合や親族が日本に居住している場合には、課税当局から日本居住者と認定されてしまう可能性があります。 つまり、形式的に海外に住所を移しただけでは日本国内に住所がないとはされません。 ・税制改正リスク 詳しくは後述しますが、富裕層が相続税の回避を目的に海外に移住するのを防ぐために度々税制改正が行われています。 改正の度に要件は厳しくなっていますので、今後も税制改正によりルールが変わってしまうリスクを移住前に認識しておく必要があります。 2-3 海外移住で相続税を回避する上で考慮すべき点 海外移住によって一定のメリットがあるのは事実ですが、それを「相続税ゼロ」に直結させることはできません。 相続税を完全に回避するには、さまざまな制約があるからです。 そのため、相続税を回避するためにはあらかじめ対策をしておく必要が出てきます。 具体的には次のような点を検討する必要があります。 ・財産を国内に残すかどうか 国内に不動産や預金を残していると相続税が課税されるため、すべて国外に移すかどうかが大きな分かれ道となります。 ・移住先国の税制や日本との租税条約の有無 例えばシンガポールは相続税がない国として知られていますが、世界にはアメリカや日本のように相続税が課される国もあります。 したがって、日本の相続税を回避したとしても移住先で相続税が課されてしまうケースもあります。 また、アメリカやフランスのように日本と相続税に関する条約を結んでいる国では、二重課税を防ぐ仕組みがあります。 一方、条約がない国では二重課税のリスクがあります。 ・名義変更手続き 実は海外に移住していた人の相続が発生した場合には、名義変更の手続きに多くの労力と時間がかかります。 現実には言語や現地の法律の問題もあるため一般の方が独力で手続きするのは不可能です。 そのため、専門家に依頼する必要があり、相続税とは別の費用がかかってしまうことになります。 相続が始まる前に「財産を贈与する」、「信託を使う」など承継方法を工夫することで、名義変更の手続きの負担を和らげることができますが、税金とは別の視点で考慮すべき論点です。 ・相続発生のタイミングと移住の時期をどう調整するか 相続開始(被相続人の死亡時)にどこに住んでいるかが重要なので、移住の計画を立てる際には「10年超」という時間軸を逆算して考える必要があります。 まとめると、「海外に移住すれば大丈夫」という単純なものではなく、「どこに住むか」「財産をどこに置くか」「承継の手続きをどうするか」を総合的に考えてはじめて、効果的な相続税対策になるのです。 第3章 10年ルールは変わるか?今後の税制改正の可能性 例え現状は「10年ルール」の要件を満たすことができると考え、海外移住を検討又はすでに海外移住していても、そもそものルールが変わってしまう可能性もあります。 この章では今までの改正の経緯と今後の改正の可能性を解説します。 3-1 日本の税制改正の経緯と今後の考察 相続税のルールは過去から何度も改正されており、海外移住による相続税回避は年々難しくなっています。 もともと日本では、相続人や被相続人が日本国籍を持っているだけで、国外財産も含めて課税されるという非常に広い課税範囲が適用されていました。 しかし、グローバル化の中で海外に生活の拠点を移す人が増え、「国外財産まで日本が課税するのは厳しすぎる」という国際的な批判も出てきました。 しかし、この国籍課税を単純に廃止して、死亡時の居住地でのみ判断をすると相続開始前に短期間だけ海外に移住して国外財産を課税対象から外すという租税回避行為が容易にできることになってしまいます。 そこで課税範囲を一部制限する仕組みとして「5年ルール」が導入されました。 この「5年ルール」では、相続開始前5年以内に日本に住所がある場合は国外財産にも課税されるという内容でした。 しかし、この「5年ルール」を導入しても、実際には富裕層が相続開始前に短期間だけ海外に移住して国外財産を課税対象から外すという事例が相次ぎました。 こうした“抜け道”が広がった結果、2017年の改正で「5年ルール」が「10年ルール」へと延長され、課税逃れが難しくされたのです。 つまり、日本の相続税法は「海外移住による課税逃れを防ぐ方向」に改正され続けており、今後も同じ流れで厳格化が進む可能性が高いと言えます。 3-2 国際的な課税権の動向 日本と同じように相続税(遺産税)を課している国がどのような仕組みになっているかも、今後の改正の可能性を考察するうえで重要になります。 例えば主要国では下記のようになっています。 ・イギリス イギリスでは相続開始前過去20年のうち15年イギリスに居住していた場合には、イギリスに住んでいる者と同様にイギリス国外の財産にも課税されます。 ・フランス フランスでは相続人が過去10年のうち6年フランスに居住していた場合には、フランスに住んでいる者と同様にフランス国外の財産にも課税されます。 ・アメリカ アメリカでは過去の居住期間に応じた取り扱いをしておらず、相続開始時の身分で米国市民(米国に住所がある者)はアメリカ国外の財産にも課税がされます。 したがって、アメリカのように居住期間にかかわらず死亡時だけで判断をする国もあれば、イギリスのようにより長期の期間で判断をする国もあります。 日本よりも長期の居住期間で課税対象の判断をしている国もあるため、日本も同様により長期間で判断することになる可能性は十分あるといえます。 3-3 海外移住を考えるなら税制改正を考慮すべき 制度は今後さらに厳格化される可能性があるため、『将来の改正』を前提に行動することが重要です。 「今は国外財産が課税されない」としても、将来的に再び課税範囲が広がる可能性は十分にあります。 前述したように実際過去にも「5年ルール → 10年ルール」と改正が繰り返されてきました。 ポイントとしてこのように改正があった場合には、相続発生時のルールが適用されることになります。 弊社にご相談があったお客様の中にも、「移住した際には5年ルールだったので5年間であればと相続税の回避を目的に移住したものの途中で10年に期間が延長され相続税は諦めて住みやすい日本に帰国した」という方もいらっしゃいます。 したがって、「今は大丈夫だから」と安心せず、数年先を見越して海外移住は検討する必要があります。 相続税制度は「抜け道をふさぐ方向」に歴史的に改正されてきており、今後も海外移住による回避はますます難しくなると考えられます。 第4章 よくあるQ&A Q1 一時帰国しても大丈夫? 結論:短期間の一時帰国であれば直ちに課税対象になることはありません。 例えば夏休みに数週間だけ帰国して日本の実家に滞在する程度であれば、日本に「住所」があるとは見なされません。ただし、1年の大半を日本で過ごす、住民票を戻す、子どもを日本の学校に通わせるなど生活の拠点が日本にあると判断されると、「日本居住」と扱われるリスクがあります。つまり滞在期間よりも「生活実態」が重要です。 Q2 10年経過したが、日本に帰国したい場合はどうなる? 結論:帰国後に相続が発生すれば、日本の居住者として課税されます。 例えば、父が海外に12年住んだ後に日本に帰国し、3年後に亡くなった場合、亡くなる直前は日本居住者ですので、国内外の財産すべてが日本の相続税の対象になります。したがって、海外移住の「10年ルール」で非課税になっていても、帰国した時点でリセットされるイメージです。 Q3 国籍は日本のままでも適用される? 結論:国籍だけで直ちに課税されることはありませんが、日本国籍者はルールの影響を強く受けます。 相続開始前10年を超えて海外に住んでいる日本国籍者であれば、国外財産は原則課税対象外です。 ただし、日本国籍を持っていると生活の拠点は日本にあるのではと疑われる傾向があります。 国籍を保持するかどうかは税務だけでなく生活全般に関わる大きな判断なので、専門家に相談しながら検討すべきテーマです。 Q4 被相続人、相続人ともに海外に移住したが、それぞれの家族が日本にいる場合は? 結論:日本に残る家族が相続人に含まれていれば、その人には日本の相続税がかかります。 例えば父(被相続人)がアメリカに10年以上住んで亡くなり、相続人の子2人のうち1人はアメリカ居住、もう1人は日本居住だったとします。 この場合、日本に住む子が相続する部分については、日本の相続税の対象になります。 つまり「家族全員が海外居住」でなければ、国外財産も含めて完全に課税を避けることは難しいのです。 Q5 相続税の二重課税になるケースはある? 結論:ありますが、外国税額控除で調整できる場合があります。 例えば、父がアメリカに住んでいてアメリカの不動産を相続した場合、アメリカでも相続税(Estate Tax)がかかり、日本でも課税される可能性があります。 こうした二重課税を避けるために「外国税額控除」という仕組みがあり、海外で支払った相続税を日本の相続税額から差し引けるケースがあります。 ただし、控除には限度があるため、全額が相殺できるとは限りません。 申告も煩雑になるため、国際相続に詳しい税理士に依頼するのが安心です。 第5章 国際相続は「税理士法人マインライフ」へ 国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑で、専門家の存在が成功の分かれ道となります。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」―― そのようなときは、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 最初の一歩を踏み出すことが、複雑な国際相続を解決へ導く最大のカギとなります。 第6章 まとめ いかがだったでしょうか。 今回のコラムを通じて、「海外に移住すれば相続税を避けられる」という単純な話ではなく、10年ルールには厳格な条件があり、国内財産は必ず課税されること、そして制度改正や国際的な課税強化の流れから今後ますます回避が難しくなることをご理解いただけたかと思います。 特に、次のような点が重要です。 ・被相続人と相続人の双方が10年を超えて海外に居住している必要がある ・日本にある財産は移住の有無にかかわらず課税される ・帰国や国籍の保持によって課税対象が広がるリスクがある ・将来の改正でさらに厳格化される可能性が高い つまり、「移住だけで相続税を回避できる」と考えるのは危険であり、資産の置き場所や移住先国の制度、国際的な動きを含めて総合的に検討することが欠かせません。 また、国際相続は制度の違い・言語の壁・申告期限の厳しさなどから、放置すると大きなトラブルに発展するリスクがあります。したがって、相続や移住を検討する段階から、できるだけ早めに専門家に相談することが安心につながります。
相続対策, 国際相続サポート
日本からアメリカへ生前贈与/ケース別でわかる税金・手続き
「日本の相続対策として生前贈与を活用したいけど、子どもがアメリカに住んでいると難しいのかな」 「アメリカの税金のことはよくわからないし」 生前贈与を相続対策として検討している方からのご質問でした。 日本にいる子供だけでなく海外にいる子どもにも平等に生前贈与を行いたいとの要望でしたが、いままでに生前贈与を海外にいる子どもへ行ったことがないため、どうしたら良いのかと悩まれておりました。 ご安心ください。国際的な贈与は注意しなければならない点はもちろんありますが、計画的に準備を行うことで安心して生前贈与を行うことが可能です。 本記事では、アメリカに住んでいる方への贈与についてのポイント・贈与税・相続税の取り扱いを専門家の視点を踏まえ解説しております。 あなたの不安を解消しますので、ぜひ最後まで読んでください。 第1章 アメリカへの生前贈与の3つのポイント 「財産を渡す側(贈与者)=日本居住」「財産を受け取った側(受贈者)=アメリカ居住」の生前贈与の3つのポイント 日本居住者からのアメリカ居住者への生前贈与は以下3つのポイントに留意する必要があります。 ポイント①日本の贈与税 財産を渡す側(贈与者)が日本居住であれば、財産を受け取った側(受贈者)がアメリカ居住でも、原則として全世界の贈与財産に日本の贈与税が課税対象となります。 受贈者は基礎控除(年間110万円)を超える場合には日本での贈与税申告が必要です。 受贈者が日本非居住者(アメリカ居住者)なので納税管理人(※下記<専門家の視点①>)の選任も必要となります。 ポイント②アメリカの贈与税(連邦税) 財産を渡す側(贈与者)が「アメリカの非居住者・非市民」なので、アメリカ国内の不動産などを贈与したときはアメリカ贈与税の対象となります。 贈与者は年間基礎控除(受贈者1人当たり19,000米ドル(2025年))を超える場合にはアメリカでの申告が必要となります。 ただし、無形財産(預金・株式などの有価証券)は、アメリカ贈与税の対象となりません。 また、州によっては州税としての贈与税が存在します。 連邦税としての贈与税はかからなくても、州税としての贈与税はかかることもあります。州税については、現地の専門家と連携し確認を行う必要があります。 ポイント③アメリカの報告義務 アメリカ居住者である財産を受け取った側(受贈者)は、外国人からの贈与の合計が年間10万米ドルを超えるとForm 3520の報告が必要となります。 ただし、授業料・医療費の学校・医療機関への直接支払は除外となります。 アメリカの手続き(贈与税申告・Form 3520の報告) 贈与額(USD) 贈与税申告 Form 3520の報告 $19,000未満 不要 不要 $19,000〜$100,000 要 不要 $100,000超 要 要 ※贈与税申告が必要な場合においてもアメリカ贈与税は一般的には生じません。(後述:第2章 具体例②) <専門家の視点👉> ①日本の納税管理人の選任・届出 海外に住む子どもなどが贈与を受ける場合、日本国内に納税管理人を選任し、税務署に「納税管理人届出書」を提出する必要があります。 提出先:海外在住者が贈与税の申告をする場合は、住所を管轄する税務署がありません。 自分で日本国内のどこかの税務署を定めてそこに届出することになります。 実際には、納税管理人の住所に合わせることが多いです。 納税管理人:誰でもなれる。日本に住む親族、信頼できる知人、または税理士が選任されるケースが多い。 役割:納税管理人は、申告書の提出や税金の納付など受贈者に代わって税務署とやり取りする法的な窓口となります。 ②アメリカ贈与税の課税の対象となる財産(財産の種類で異なる) 贈与者がアメリカ非居住外国人(アメリカ市民ではなくアメリカに住んでいない人)である場合、そもそもアメリカ贈与税の対象はアメリカ国内の財産のうち無形財産以外に限られます。 無形財産:預金、株式・債券等の有価証券など 無形財産以外:不動産、現金など したがって、日本からアメリカへの生前贈与の多くのケースである預金の贈与ではアメリカの贈与税は課税されないこととなります。 ③アメリカの報告義務(Form 3520) アメリカに住む子どもなどが日本から贈与を受けた場合、「Form 3520」をIRS(日本の国税庁に相当する機関)に提出しなければなりません。 提出基準:年間10万米ドルを超えるアメリカ非居住外国人からの贈与を受けた場合に義務発生。 提出期限:翌年4月15日(延長申請をしていれば延長後の期限まで) 罰則:未提出の場合、贈与額の最大25%に相当するペナルティが課されることがあります。 したがって、日本側で贈与税をきちんと申告・アメリカでの贈与税がかからない場合でも、報告を怠れば重大なリスクを抱えることになります。 <財産の種類別「日本×アメリカ」早見表> (前提:贈与者=日本居住(アメリカ非居住外国人)、受贈者=アメリカ居住) 贈与する財産の種類・所在地によって両国の税金・手続きが以下の通り変わることになります。 贈与財産 ①日本の贈与税 (受贈者) ②アメリカの贈与税 (贈与者) ③Form 3520 (受贈者) 日本の不動産 課税対象(国内財産) 対象外 $100,000超なら提出 アメリカの不動産 課税対象(国外財産) 対象(アメリカ内不動産) →申告が必要 $100,000超なら提出 預金の送金 (日本口座) 課税対象(国内財産) 対象外 $100,000超なら提出 預金の送金 (アメリカ口座) 課税対象(国外財産) 対象外(無形資産) $100,000超なら提出 現金 (アメリカで手渡し) 課税対象(国外財産) 対象(アメリカ内で手渡し) →申告が必要 $100,000超なら提出 授業料・医療費 (学校・病院へ直接支払) 生活費・教育費の“通常必要”なら日本も原則非課税 対象外 Form 3520不要 第2章 アメリカへの生前贈与のよくある具体例(贈与税について) 「財産を渡す側(贈与者)=日本居住」「財産を受け取った側(受贈者)=アメリカ居住」の生前贈与の具体例 ここでは、日本居住者からのアメリカ居住者への生前贈与をよくある具体例を基に各国の「贈与税」を確認していきます。 具体例①:預金の海外送金「110万円」 ①日本の贈与税:申告不要 / ②アメリカの贈与税:なし / ③Form 3520:不要 ① 日本の贈与税 贈与者が日本居住のため、原則、全世界の贈与財産が課税対象となります。 贈与税:110万円 − 基礎控除110万円 = 0円(申告不要) ※年間の贈与額が110万円を超えない年は申告不要。 ② アメリカの贈与税 贈与者はアメリカ非居住外国人(アメリカ非居住・非市民)で、贈与した預金は無形財産。 アメリカ贈与税の対象はアメリカ国内の不動産などの無形財産以外に限られるため課税されません。 ③ Form 3520 アメリカ非居住外国人からの贈与が年間100,000米ドル超で提出義務が発生します。 110万円は100,000米ドル以下であるため不要。 具体例②:預金の海外送金「1,500万円」(100,000米ドル超(145円/1米ドル)) ①日本の贈与税:(受贈者)申告・納税必要 / ②アメリカの贈与税:なし / ③Form 3520:(受贈者)必要 ① 日本の贈与税 贈与者が日本居住のため、原則、全世界の贈与財産が課税対象となります。 贈与税額:366万円 ※税額:1,390万(1,500万円−基礎控除110万円)× 40% − 190万 = 366万円 (注)続柄や他の贈与の有無で税率は変わる場合があります。 申告・納付:受贈者は翌年3/15までに日本で申告・納付する必要があります。 受贈者は日本の非居住者のため、納税管理人の届出書をあわせて提出。 <専門家の視点👉> 生前贈与を一括で行わない相続対策の検討(贈与税率の観点) 例えば半額の750万円の贈与の場合には贈与税額は102万円となります。日本の贈与税率は累進課税(一回の贈与額が大きいほどに税負担が大きい)のため検討の余地があります。 ② アメリカの贈与税 贈与者はアメリカ非居住外国人(アメリカ非居住・非市民)で、贈与した預金は無形財産。 アメリカ贈与税の対象はアメリカ国内の不動産などの無形財産以外に限られるため課税されません。 <専門家の視点👉> もしアメリカ内不動産などのアメリカ国内財産の贈与であれば、年間基礎控除(19,000米ドル(2025年))を超えるため、アメリカ贈与申告が必要になります。 なお、日本人贈与者には「統一移転税額控除(日本人は特例的に適用あり)」という約20億円の大きな控除(一定の調整計算が必要です)が認められるため贈与税はめったにかかりません。 ③ Form 3520 アメリカ非居住外国人からの贈与が年間100,000米ドル超で提出義務が発生します。 100,000米ドルを超えるため提出が必要となります。 <専門家の視点👉> 不提出は贈与額の最大25%に相当するペナルティが課されることがあります。 アメリカ贈与税がかからない場合は特に手続きが漏れるケースが散見されますので確実に提出するようにしましょう。 第3章 アメリカへの生前贈与のよくある具体例(相続税について) 「財産を渡す側(贈与者)=日本居住」「財産を受け取った側(受贈者)=アメリカ居住」の生前贈与の具体例 第2章で確認した生前贈与のその後を各国の「相続税(アメリカ遺産税)」で確認していきます。 日本・アメリカの両国ともに生前贈与された財産は、のちに贈与者に相続があった場合には相続財産に加算して相続税(アメリカ遺産税)を計算することになります。 日本では、原則死亡前7年以内の贈与が相続税に加算され、既に納めた贈与税は相続税から控除します。 アメリカでは、生前の課税贈与(1977年以降)を原則すべて遺産税の計算基礎に合算し、既に納めた贈与税は遺産税から控除します。 具体例①:預金の海外送金「110万円」 ①日本の相続税 死亡が贈与後7年以内の場合には生前贈与の110万円を相続時の亡くなった人(被相続人)の遺産に加算して(贈与はなかったものとみなして)相続税を計算します。 死亡が贈与後7年超の場合には生前贈与の110万円を遺産に加算する必要はありません。 ②アメリカの遺産税 贈与財産(預金)は無形財産で、生前贈与時点ではアメリカ贈与税の課税対象外です。 したがって相続時にアメリカ側の生前贈与分の持ち戻しは通常生じません。 <専門家の視点👉> 日本の相続税は贈与から7年経過しているか否かにより贈与財産を遺産に加算するかどうか取り扱いが異なります。 言い換えると生前贈与の相続対策は、贈与時から7年経過して初めて効果を発揮します。 よって将来を見据えて早めに相続対策を行う必要があります。 具体例②:預金の海外送金「1,500万円」 ①日本の相続税 具体例①と同様に贈与時から7年を経過しているかにより相続税の計算が異なります。 贈与後7年以内の場合には、すでに納付した贈与税(366万円)を相続税の一部に充てることができます。 ②アメリカの遺産税 具体例①と同様に相続時にアメリカ側の生前贈与分の持ち戻しは通常生じません。 実際には、皆さまが検討している生前贈与の金額に応じて日本・アメリカの税額・手続きを検討していくことになります。日本・アメリカ両国とも生前贈与の金額によって、とるべき手続き・税額も異なってくることに留意する必要がございます。特に生前贈与の金額が多額になるケースについては専門家へ相談する必要出てくるでしょう。 第4章 国際相続・贈与の相談は「税理士法人マインライフ」へ 贈与が国際間をまたぐものであるため手続きが複雑になるかもしれない・・・。 そのような難しいケースでも、弊社には最適なサポート体制が整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 強み 内容 ① 国際相続の経験が豊富な専門家が直接対応 少数精鋭体制で、経験豊富な税理士が必ず対応。 担当が途中で変わる心配がありません。 ② 相続税申告・対策に特化し、豊富な実績 相続専門の法人だからこそ、相続に特有の実践的なノウハウが蓄積されています。 ③ 海外案件にも強い独自ネットワーク 海外の専門家との連携体制が整っており、海外の財産や海外在住者の手続きに対応が可能です。 ④ 申告だけでなく、相続対策にも精通 単なる税計算だけではなく、納税資金対策や二次相続対策など、将来を見据えたオーダーメイドの提案が得意です。 「生前贈与を行いたいけれど子どもがアメリカに住んでいるからどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第5章 まとめ いかがだったでしょうか。 相続対策としてアメリカに住んでいる子どもへの生前贈与の活用を検討中のあなたも留意点や具体的な税金のイメージが湧いたのではないでしょうか。 アメリカ居住者への贈与についての3つのポイント「①日本の贈与税」「②アメリカの贈与税(連邦税)」「③アメリカの報告義務」を解説しました。 また、具体例に基づき「贈与税・相続税」の税額を解説しました。 実務的には、当然ですが皆さまが検討している生前贈与の金額に応じて日本・アメリカの税額・手続きを検討していくことになります。 そこで大切になるのは日本とアメリカ双方の制度に精通した税理士や現地専門家です。 手続きの漏れや課税リスクを回避するためにも専門家への相談が最善の方法になります。
国際相続サポート
相続税の外国税額控除とは?制度概要と日本で適用する手続きの全体像
「父がアメリカで購入したマンションや株式を相続することになった。日本の相続税とアメリカの相続税の二重課税を回避する方法があるらしいけど」 海外に財産がある相続では、日本と海外の両国で相続手続きが必要になります。 調べていくと「外国税額控除」という制度の存在を知ることになりますが、仕組みが専門的で複雑なため、「自分の場合に本当に使えるのか」「二重課税は避けられるのか」と迷ってしまうことも多いでしょう。 そうなんです。外国税額控除は初めての方にはとても分かりづらい制度です。 でも、海外と日本の両方で課税される可能性がある相続において、「外国税額控除」は二重課税を調整するために欠かせない大事な仕組みなのです。アメリカにある財産を日本に住んでいる人が相続した場合などは、実際に両国で課税されることがあり、その調整のために活用できるのが「外国税額控除」です。 もっとも、外国税額控除があれば全てが解決するわけではありません。控除できるのは海外にある財産に対応する「日本の相続税額」が上限であり、米国の州税のように対象外となる税金もあります。 また、日米租税条約によってアメリカでは超富裕層でなければ相続税がかからないケースも多く、そもそも二重課税自体が発生しない場合も少なくありません。 アメリカ以外の国で考えるとフランスやドイツのように相続税が発生しやすい国もあれば、シンガポールのように相続税が存在しない国もあります。 つまり、「外国税額控除」の適用については現地で相続税が発生しているのか、二重課税になっているのかということも考える必要があります。 本記事では、相続税における外国税額控除の基本と、その限界や注意点をわかりやすく解説します。 控除を使えるのに使わないのはもったいないです。 「使える控除は必ず使う」ための知識を身につけてください。 第1章 相続税の外国税額控除とは 相続税の外国税額控除とは、同じ財産に対して日本と外国の両方で相続税がかかるときに、二重課税を調整するための制度です。 この制度を理解する上で、まずは相続税の外国税額控除の目的や仕組みを整理します。 1-1 制度の仕組み 【日本の相続税の課税方法】 日本では、亡くなった方や相続人が日本に住んでいる場合、国内の財産だけでなく海外の財産も含めて相続税の対象になります。(全世界課税) 【相続税の外国税額控除の制度趣旨】 財産が相続税制度のある国に所在し、その国でも相続税が課される場合は、二重課税になります。 そこで日本では、外国で支払った相続税を日本の相続税から差し引けるようにしており、その調整の仕組みが「相続税の外国税額控除」です。 【例外】 日本国内の財産は日本で課税されるべきものと考えられているため控除の対象外です。さらに海外の財産についても、日本でその財産に課される相続税の金額が限度になります。 この「限度」については、後ほど計算方法とともに解説します。 1-2 二重課税は本当に起きるのか(アメリカ/他国事例) 実は、外国の相続税制度の関係で二重課税にならないことも多いです。 相続税の外国税額控除が必要になるのは、日本と外国の両方で相続税が課されるときなので二重課税になっていなければ適用する必要がありません。 そのため、まずはその国において相続税が課税されるのかを確認することが必要です。 代表的な国について整理します。 アメリカの場合 アメリカでは、非居住者(米国内に住んでいない人)が米国内に財産を持っていると原則相続税が課されます。ただし非居住者の基礎控除は6万ドルしかありません。 ところが、日米相続税条約によって、日本人にも米国市民と同じ大きな基礎控除(2025年時点で約1,400万ドル)が認められます。 (この基礎控除額については改正が多く、金額も大きく変動しますのでご注意ください。) そのため、超富裕層でない限りアメリカで相続税が課されることにならず、結果的に二重課税は発生しないことが多いのです。 二重課税がなければ相続税の外国税額控除を使う必要はありません。 ただし、注意点もあります。アメリカには連邦税とは別に州ごとの相続税制度があります。 しかも、日本の相続税と州税が重なっても、外国税額控除の対象にはなりません。これは、相続税の外国税額控除の対象は「外国の国税」に限られているからです。 アジアの場合 シンガポールや香港などでは、そもそも相続税制度自体が存在しません。現地で課税されることはなく、日本の相続税のみがかかることになります。 したがって、外国税額控除を使う必要はありません。 欧州の場合 フランスやドイツなどは相続税(遺産税)が多くのケースで課税されることになっており、日本に住む相続人にも課税されることがあります。 この場合、日本でも相続税が課税され、さらにフランスやドイツでも相続税が課税されるため、相続税の外国税額控除の適用を受けることになります。 このように、国によって相続税の制度は様々です。まずは亡くなった方が所有していた財産がある国において相続税が発生するかの確認をするようにしましょう。 1-3 計算方法と「日本の相続税が限度」となる考え方 それでは、相続税の外国税額控除の計算方法とその考え方について解説します。 外国税額控除は、海外にある財産についてその国で支払った相続税に相当する税金を控除できます。ただし、その財産に対応して日本で課税される相続税の金額が限度となります。 算式で表すと以下の通りです。 【相続税の外国税額控除の計算】 ※①と②のいずれか少ない金額 ①海外で支払った相続税に相当する税金(外国の国税に限る) ②日本の相続税額 ×(海外にある財産の金額 ÷ 相続財産全体の金額) ②は海外にある財産について日本で課税される相続税を計算しています。 少し複雑なので具体的な金額を用いて確認します。 前提 ・相続財産の合計:1億円(国内7,000万円+国外3,000万円) ・日本の相続税額:1,000万円 ・外国で支払った相続税額:400万円 ➀ 400万円 ➁ 1,000万円 ×(3,000万円 ÷ 1億円)= 300万円 →控除できるのは少ない方の②300万円となります。 この図の通り、②は国外財産に対してかかる相続税額を計算しています。 外国税額控除を適用した後、日本で支払う相続税は 1,000万円 − 300万円 = 700万円 です。 このケースでは、国内財産に対応する相続税だけを日本で納めることになります。 もし、①の外国で支払った税額をそのまま全額控除してしまうと、国内財産に対応する相続税まで差し引くことになり、制度の趣旨に反することになります。 計算の方法について、確認できたと思いますので次章では実際に外国税額控除の適用を受けるための手続きや注意点について解説いたします。 第2章 外国税額控除の実務と注意点 外国税額控除を受ける場合でも、日本の相続税申告と同時に進める必要があります。 海外の手続きに時間がかかったとしても日本の相続税の申告期限は変更されませんので、注意してください。 2-1 相続税の申告と手続きの流れ 相続税の外国税額控除の適用を受ける場合は、相続税申告と同時に手続きを行います。 申告の際には、相続税申告書の「第8表(外国税額控除に関する明細書)」に必要事項を記載し、添付して提出する必要があります。 なお、日本の相続税申告は原則として相続開始から10か月以内が期限ですのでご注意ください。 【相続税申告書第8表】 (出典:国税庁) さらに、その財産が所在する国で課税されたことを証明する書類、例えば現地の申告書や課税証明書、納税証明書などを添付する必要があります。 これらは外国語で発行されるため、通常は日本語訳を付けて提出します。 2-2 外国税額控除の制度を適用する場合の注意点 既に触れた内容もありますが、相続税の外国税額控除を利用する際には、次の点に特に注意が必要です。 ① 控除の対象は国外財産のみ 外国税額控除の対象となるのは、国外にある財産にかかる相続税です。 日本国内にある財産については、日本で課税されるのが原則であり、控除の対象にはなりません。 ② 州税や地方税は対象外 アメリカなど一部の国では、連邦税に加え、州ごとに独自の相続税が課される場合があります。 しかし、外国税額控除の対象は「外国の国税」に限られるため、州税や地方税については日本で控除することはできません。 このため、州税が課された場合には、日本の相続税と二重に負担するケースもあります。 ③ 海外の申告書類の準備が不可欠 外国税額控除を適用するには、その国で相続税を支払ったことを証明する書類(課税証明書や納税証明書)を添付しなければなりません。 海外の申告や証明書の作成が遅れると、日本の申告期限に必要書類が間に合わないことがあります。 したがって、現地の専門家(税理士・会計士・弁護士など)と連携して書類を揃えることが実務上不可欠です。 第3章 外国税額控除でよくある質問(Q&A) Q1. 日本の申告期限(10か月)に海外の課税証明が間に合わない場合は? 間に合わなくても控除は可能です。 まずは外国税額控除の適用を受ける前の金額で一度日本の相続税申告書を期限内に提出し、その金額で納税します。 その後、海外の課税証明が発行できた段階で、更正の請求を行い還付を受けることが可能です。 日本の相続税の申告期限は相続開始から10か月ですが、海外の期限は必ずしも一致せず、税金の確定まで長い時間を要する場合もあります。 海外の手続きは時間がかかることが多いため、早めに現地の専門家と連携し、スケジュール管理を徹底することが重要です。 Q2. 外国で支払った税金はどの為替レートで換算しますか? 原則としてその外国で納付すべき日のTTS(対顧客電信売相場)で円換算します。 通常は国内から送金した日のTTSも使えますが、送金が大きく遅れた場合は注意が必要です。 Q3. 相続に関連して発生した税金はすべて外国税額控除の対象になりますか? すべての税金が控除できるわけではありません。あくまで控除の対象は「相続税に相当する税」に限られます。 国によっては相続手続きの際に消費税や不動産取得税に相当する税金が課される場合もありますが、相続税に相当するものではないため控除の対象外です。判断が難しいケースもあるため注意が必要です。 Q4. 日本と違って、亡くなった人の遺産そのものに課税される国の場合は控除の対象になりますか? 亡くなった人の遺産そのものに課税される国(アメリカやフランスなど)であっても、日本の相続税に相当すると認められる税であれば外国税額控除の対象になります。 日本の相続税は「相続人ごと」に課税されますが、国によっては「被相続人の遺産全体」に課税されます。方法が違っても、その性質が相続税に相当すれば控除の対象となります。 Q5. 相続税の計算上、控除できる債務がある場合はどのように計算しますか? 国外財産については、その財産に対応する債務を差し引いた後の価額を用います。国内財産についても同様に債務控除後の価額を基準にします。 つまり、相続人が実際に引き継ぐ純粋な価値部分をもとに外国税額控除を計算します。 第4章 相続税の外国税額控除の適用がある場合は、国際相続に強い税理士の支援が必要 相続税の外国税額控除は、単に日本の相続税を計算するだけでは適用できません。 海外の課税証明書や現地申告書類を揃える必要があり、現地の専門家との連携が不可欠です。 そのため、海外に財産がある相続の場合には、国際案件に強い税理士に相談することが大事です。 ① 税理士にも得意・不得意分野がある 相続業務を日常的に扱っていない税理士も多く、中には年に1件も相続案件を担当していないという税理士も存在します。特に海外が関係する相続となると、いままでまったく経験がない税理士も多く、思わぬトラブルや遅延の原因となり得ます。 税理士であれば誰でもいいということはなく、実績や専門性を見極めて依頼することが大切です。 ② 各国の法律や制度が異なり、現地の専門家との連携が必要なこともある 国ごとに制度が異なるため、日本国内だけでは完結できない手続きが発生することがあります。 国際相続に強い税理士であれば、現地の弁護士や会計士と連携できるネットワークを持っているケースが多く、安心して任せられます。 経験のない税理士に依頼すると、自分で現地の専門家を探す必要に迫られることにもなりかねません。 ③ 国際相続でなくてもタイトなスケジュールがさらにシビアに 相続税の申告期限(10か月以内)は海外の手続きがあるからといって延長されません。海外の手続きはかなり時間がかかり、準備や判断の遅れが致命的になり得ます。 こうしたケースに慣れた税理士でなければ、期限に間に合わないリスクが高まります。 ④ 状況に応じた柔軟で迅速な判断と対応が求められる 海外の申告や手続きなどはその国の法律が関係し、国際相続は一筋縄ではいかないことがほとんどです。 その都度、適切に判断し、書類の整備や申立て方法を柔軟に変更できるかどうかが結果を左右します。 国際相続の経験が豊富な専門家であれば、こうした事態にも迅速・的確に対応でき、スムーズに手続きを進めることができます。 第5章 ご相談は、信頼と実績の「税理士法人マインライフ」へ 海外に財産があり、その国でも税金が発生する??―― そのような難しいケースでも、最適なサポート体制が弊社には整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」―― そのようなときは、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 第6章 まとめ いかがでしたでしょうか。ここまで、相続税の外国税額控除について解説してきました。 ・相続税の外国税額控除は、日本と外国の両方で相続税が課された場合に二重課税を調整する制度。 ・二重課税は必ずしも発生せず、アメリカやアジアでは課税がないケースも多い一方、欧州では二重課税が起きやすい。 ・控除額は①外国で支払った税額と②日本側の算式で算出した額のうち少ない方が上限。 ・国内財産や州税・地方税は対象外であり、控除できるのは「外国の国税」に相当する税金に限られる。 ・申告には「第8表」への記載と海外の課税証明の添付が必要で、日本の申告期限は相続開始から10か月。 ・実務では為替換算や期限のズレ、対象税目の判定など複雑な点が多く、海外の専門家との連携が不可欠。 海外に財産がある相続は、一般の相続以上に準備や判断が難しくなります。外国税額控除を正しく適用し、損をしないためにも、国際相続に強い税理士に早めに相談することをおすすめします。
国際相続サポート
知らなきゃ損する!海外口座の相続手続きガイド
「海外に預金口座がある場合、相続手続きはどう進めればいいのか――。」 近年は海外赴任や留学、移住などで海外の銀行口座を開設する方が増えています。 帰国時に解約するケースもありますが、金利や利便性の面から、口座を残したまま日本に戻る方も少なくありません。 しかし、いざご家族が亡くなったとき、海外口座は日本の預金口座と同じ手順では進まないのが実情です。 国によっては裁判所の手続き(プロベート)が必要になったり、翻訳・認証(アポスティーユ等)を求められたりして、想定以上に時間と手間がかかることが多いです。 このコラムでは、海外の預金口座を相続する際の一般的な手続きについてわかりやすく解説しますが、実際に手続きを行う際には国際相続に精通した専門家に依頼することを強くおすすめいたします。 第1章 国によって異なる海外口座の相続手続き 海外口座の相続は、ざっくり言うとプロベート手続きが必要なものと不要なものの2タイプに分かれます。 また、国のルールに加えて、銀行や各自治体(州など)が定めたルールを把握する必要があります。 1-1 プロベートが必要な国 アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、香港、シンガポールなどの国では、銀行が相続人だけの申告で払い戻しをしてくれないことが多く、裁判所でプロベート手続きが必要になります。 そのため相続発生時には、相続人は ① 口座情報の把握・受取人指定の有無の確認と、金融機関への死亡連絡(口座凍結) ② 現地裁判所でプロベート(遺産清算手続)を申立て、権限を証明する書面を取得 ③ ②の裁判所で取得した書面+死亡証明書等を金融機関へ提出し、払戻し・解約・相続人(または遺産)名義への移管/送金を実行 という手続きを踏んで、口座の相続を行なっていきます。 プロベートとは、裁判所が遺言の有効性や遺産管理の権限(遺言執行者・遺産管理人)を確認し、遺産の管理・分配を公的に進めるための手続きです。 ※プロベートの詳しい概要は下記の別記事で解説しています。 https://www.mine-life.jp/what-is-probate-working-flow-how-to-avoid-2 1-2 プロベートが不要(または中心ではない)国 フランス、ドイツ、イタリアなどのEUでは、裁判所のプロベートではなく、現地の公証人に依頼をして、相続人であることを証明する書類(相続証明書(Certificate of Heirship)や欧州相続証明書(European Certificate of Succession)等)を作成して、それらをベースに銀行手続きが進むことが多いです。 そのため相続発生時には、相続人は公証人を通じて、 ① 金融機関へ死亡の連絡をして、口座の入出金停止(凍結)を行う ② 相続人の確定と、解約(払戻)に必要な書類を整える(例:日本では、「被相続人・相続人の戸籍謄本等」、「印鑑証明書」、「遺言書」または「遺産分割協議書」など) ③ 金融機関所定の相続書類(払戻請求書/相続届など)と②の書類を提出し、解約・払戻(相続人代表口座への振込等)を実行 という手続きを踏んで、口座の相続を行なっていきます。 1-3 国のルールに加えて、銀行や各自治体での運用ルールも把握が必要 同じ国でも、銀行や各自治体(州など)によって運用が違うのは海外相続でよくあることです。 たとえば、以下のようなものがあります。 ・残高が小さいと「簡易手続き」が使えるケースがある ・共同名義口座は形態により自動的に共同名義人が相続することになるケースがある つまり最初にやるべきは、「日本の相続の常識」で突き進むより、その預金に必要な手続きを見極めることです。 次章以降、海外に口座を保有している方が亡くなった場合に実際に取るべき手続きを順に追って解説していきます。 第2章 海外口座の相続でまず確認したいこと この章では、相続が発生した際にまず確認すべきことを解説していきます。 2-1 相続の基本情報を確認する 相続手続きにおいて「相続人は何人いるのか」、「財産はどのようなものがあるのか」、「財産はどこにあるのか」等の基本情報を最初に整理しておくと、銀行・専門家への相談が一気に進みます。 ・亡くなった方と相続人の関係・人数 被相続人の出生から死亡までの戸籍情報を取得し、法定相続人を確定していきます。 ・財産が所在している国・種類 どのような財産がどの国にあるか整理します。 ・名義(単独名義・共同名義など) プロベート国では特に、共同名義・受取人指定(POD/TOD等)があると手続きの方法が変わることがあります。 2-2 手続きと相続税のスケジュールを確認する 海外に財産がある場合には、日本の相続税の申告期限等とのスケジュール管理が重要になります。 日本の相続税は、死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。 一方で、プロベートが必要な国は10か月以内に現金化まで終わらないことも普通にあります。 なので、実務では、 ・「海外口座の名義変更・解約・送金」が終わる時期の目安を置く ・終わらない前提で、相続税申告にどう織り込むか(評価資料の取り方、申告の仕方)を先に決める という順番で進めるのが安全です。 第3章 海外口座の名義変更とお金の受け取り方を確認する 日本の銀行口座の相続手続きは「戸籍の一式」と「遺言書又は分割協議書」を提出すれば手続きを進めることができますが、海外口座の相続は、「戸籍を出せば終わり」という話になりにくいのが特徴です。 ポイントは、その国がプロベート(裁判所手続き)が必要な国か/不要な国かで、銀行に求められる“手続きの型”が変わるということです。 ここでは、実際にお金を受け取るまでに押さえるべき流れを、3つに分けて解説します。 3-1 海外の銀行に出す書類を確認する 海外の銀行が確認したいのは、次の3点です。 「①亡くなった事実」「②相続人は誰か」「③誰に払ってよいか」 この3点を示すために、大きく3つの分類の書類が必要になります。 (1)死亡の証明+身分関係の証明(誰が亡くなり、誰が家族か) ・死亡証明(死亡診断書・死亡証明書など) ・戸籍一式(出生から死亡までつながるもの) ・相続人の本人確認書類(パスポート等) 日本で取得した原本を提出することが多いです(コピーでもよいかは各銀行に確認することをおすすめします) (2)「受け取る権限」の証明(誰が受け取り担当者か) ここが国によって一番変わるポイントです。 ・プロベートが必要な国: 裁判所によるプロベート手続きが原則必要になります。(共同名義財産や受取人指定財産の場合は必要でないケースもあります) ・プロベートが不要(中心ではない)国: 相続証明書・公証人の証書※など、「相続人(または受取人)が誰か」を示す書類を準備して進めることが多いです。 ※相続証明書・公証人の証書:国によって呼び方は違いますが、目的は共通で 「この人が相続人/遺産を受け取る権限者です」 を第三者(銀行など)に示す書類です。一般的には、口座のある国(現地)の公証人が発行・作成する相続人(受取権限)を証明する公式書類 が該当し、現地の公的なホームページを確認又は現地の弁護士に依頼して各国ごとに異なる「必要書類」を取得する必要があります。なお、EUにおいて公証人が作成した証書は、EU圏内であれば他の国でも共通して使うことができます。 (3) 翻訳・公的な証明(認証/アポスティーユ等) 海外の銀行は「公的に正しいと確認できるか」を重視します。 そのため、翻訳や、翻訳証明、公的証明が不足すると、いったん提出したにもかかわらず「認証が足りない」、「翻訳が正式ではない」として差し戻しにあい、再提出で時間が延びるということがよくあります。 最初から「翻訳の要否」「翻訳証明の要否」「認証/アポスティーユの要否」を確認しておくと、遠回りを防げます。 アポスティーユとは、外国で公文書を提出する際に領事認証等を省略できるよう、発行国の当局がその公文書の真正(署名者の資格・署名・公印など)を証明する認証(証明書)です。 3-2 相続人どうしのお金の分け方を確認する 海外口座は、銀行にとっては「誰に払えばトラブルにならないか」という点が重要になります。 したがって、確認ができるまでは預金の払い出しはできず、相続人の間で「受け取り方」を先に決める必要があります。 (1)プロベートが必要な場合(裁判所手続きが中心) 遺産管理者が口座を回収し、あとで相続人に分配する流れになることが多いです。 銀行側も「遺産管理者に払う」前提で話が進みます。 (2)プロベートが必要でない場合(相続人証明が中心) EUでは遺言がなければ法定相続人に分配されることになるか、また、相続人が「誰が受け取るか」を書面で合意し、銀行に提出する流れになることもあります。 → 相続人全員の署名を求められることもあります。 また、日本で作る「遺産分割協議書」がそのまま通るかはケース次第です。 海外では、日本の遺産分割協議書は「私文書」なため遺産分割協議書だけでは手続きが進まないことも多々あります。また、署名方法(サイン証明)や言語、内容等が現地と異なるため、現地専門家と連携して手続きにあたる必要があります。 3-3 海外から日本の口座にお金を送る方法を確認する 送金は「できる/できない」より、「止まらずに通す」のがポイントになります。 事前に次の事項を押さえておくとスムーズです。 (1)両替のタイミング(円換算のズレに注意) 相続税の計算や相続人同士の分配では、円換算が絡みます。 「いつのレートで円に直すか」を決めておくと、後から揉めにくくなります。 (2)送金の限度額・手数料(受取側の条件もセットで確認) 海外送金は、銀行側の限度額や中継銀行の手数料で、想定より目減り・遅延が起こりがちです。 また、受取側(日本の銀行)にも「着金時に必要な情報」「目的の確認」など着金のための条件が設定されていることがあります。 (3)チェックされやすいポイント(書類不足は「保留」の原因) 相続による送金は不自然な取引ではありませんが、マネーロンダリング対策の観点で確認が入ることがあります。 このときにポイントになるのが、「お金の出どころ(亡くなった方の口座であること)」、「受取人が正当な相続人であること」等が書類で説明できることです。 必要書類をそろえておくと、銀行から照会が来ても送金手続が止まりにくくなります。 第4章 日本の相続税のルールと届出を確認する 海外に預金口座があっても、条件によっては日本の相続税の対象になります。 しかも相続税の申告は、「亡くなったことを知った日の翌日から10か月」が期限です。 海外の手続きは長引きやすいので、税金の確認は早めに進めるのが安全です。 また、相続手続きが終わらない前提で、相続税申告にどう織り込むか(評価資料の取り方、申告の仕方)を先に決める必要があります。 4-1 海外口座に日本の相続税がかかるか確認する まず整理したいのは、次の3点です。 (1) 被相続人・相続人の「居住関係」 「亡くなった方や相続人が、いつ・どこに住んでいたか」で、日本の相続税のかかり方が変わります。 まずは住んでいた国・期間などの基本情報をまとめます。 居住地による日本の相続税のかかり方は、簡易的にまとめると下記のフローチャートで判断できます。(簡易的なフローチャートですので、最終的には専門家又は税務署でご確認ください) (2) 対象資産の範囲(何が相続財産になるか) 海外口座でも、預金だけでなく、証券口座・保険・年金口座などが混ざっていることがあります。 口座の種類まで確認します。 (3) 評価(いくらとして申告するか)と根拠資料 基本は死亡日時点の残高をベースに、銀行のステートメント(残高証明・取引明細など)で裏付けます。 期限までに申告できない又は少なく申告すると、加算税や延滞税がかかることもあるため、資料集めは優先度が高いです。 4-2 CRS制度について 「海外口座だから税務署に分からないだろう」とは言いにくい時代になっています。 CRS(共通報告基準)は、各国の税務当局が、金融機関から受け取った「非居住者の口座情報を、相手国の税務当局へ年1回まとめて自動的に提供(交換)」していく仕組みです。 つまり、海外口座の申告は「見つかるか見つからないか」ではなく、きちんと説明できる形で申告できるかが大切になります。 4-3 海外側で必要になる税金の手続きを確認する 国によっては、海外側で相続に関する税金(相続税・遺産税に類するもの)や手数料がかかることがあります。 日本の相続税と重なる可能性もあるため、必要に応じて条約や外国税額控除などを含めた検討が必要になります。 海外の制度は国ごとに差が大きいので、日本と現地の両方を見られる体制で進めるのが安心です。 【国外財産調書について】 海外資産の状況によっては、相続とは別に「国外財産調書」の提出対象になることがあります。 (1)誰が出す?(対象者) 原則として、日本居住者(非永住者を除く)で、12月31日時点の国外財産の合計額が5,000万円超の方が対象です。 (2)いつまでに出す?(提出期限) その年の翌年6月30日までに、所轄税務署へ提出します。 (3)相続があった年の注意点 相続開始年の国外財産調書は、相続や遺贈で取得した国外財産を記載しないで提出できる取扱いがあります(提出義務の判定も一定の除外あり)。 (4)出し忘れ・不備の影響(ペナルティ) 期限内提出があると、国外財産に関する申告漏れがあった場合に加算税が5%軽減される一方、提出がない・記載がない場合は5%加重されることがあります。 また、虚偽記載や正当な理由のない未提出は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となる可能性があります。 第5章 金額が小さい海外口座も相続税申告の対象 「残高が少ない海外口座」をどう扱うかは、手間とのバランスが悩みどころです。 海外口座の相続手続きは、前述したように海外で行う手続きも多く専門家に任せるのはコストもかかります。 そのため実務的には、多めの概算の金額で相続税申告は行い、相続手続きは行わないということもありえます。 例えば仮にアメリカに口座残高1,000ドル(約15万円)の預金口座があるとします。 この預金口座を相続する際に、現地の専門家に依頼をすると100万円かかってしまう場合、預金口座の残高よりも報酬の方がかかってしまうため手続きをしないということもあります。 ただし、相続税申告においてはたとえ1,000ドルでも申告に含めなければ申告漏れになってしまうので申告は必ず行う必要があるということです。 この章では、具体的に少額の海外口座の場合の相続手続きの考え方を解説していきます。 5-1 申告に入れない場合のリスクを確認する 少額だからといって「申告しない」判断は、後から説明が難しくなることがあります。 相続税は期限があり、申告が遅れたり申告額が少ないと加算税・延滞税がかかる場合があります。 さらに、CRSのような仕組みで口座情報が把握され得る点も踏まえ、「省略してよいか」ではなく、「現実的にいくらで計上するか」を考え、資料の収集、検討するのが得策です。 5-2 手間・費用とリスクを比べて方針を決める まずは、専門家報酬・翻訳費用・認証(アポスティーユ等)・送金手数料の目安を把握する必要があります。 「回収して日本へ送金」「回収は時間をかけつつ、申告は期限に間に合わせる」など、対応パターンを整理する こともあります。 迷う場合は、先に「税務側だけ固める」発想(評価資料の確保・申告方針の決定)が安心です。 第6章 専門家に相談して安全に手続きを進める 海外口座の相続は、海外での手続きが必須になり、現実的に専門家のサポートなしに手続きを進めることは困難です。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」―― そのようなときは、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 最初の一歩を踏み出すことが、複雑な国際相続を解決へ導く最大のカギとなります。 第7章 まとめ いかがだったでしょうか。 本記事では、海外口座の相続について ・国によってプロベートが必要なケース/不要なケースがあること ・日本の相続税の申告期限(10か月)を意識して、スケジュールを逆算する必要があること ・戸籍・翻訳・認証、現地の相続証明書など、日本とは異なる書類や手続きが求められること ・残高が少ない口座でも、申告や対応方針をあいまいにしない方が安全なこと ・日本と海外双方の制度を見ながら、専門家と連携して進める重要性 といったポイントをコンパクトに整理しました。 海外口座の相続は、「とりあえず日本と同じようにやってみる」と行き詰まりやすい分野です。 ご自身だけで抱え込まず、早めに全体像とリスクを把握し、専門家へ相談しながら、無理のないスケジュールと方法で進めていきましょう。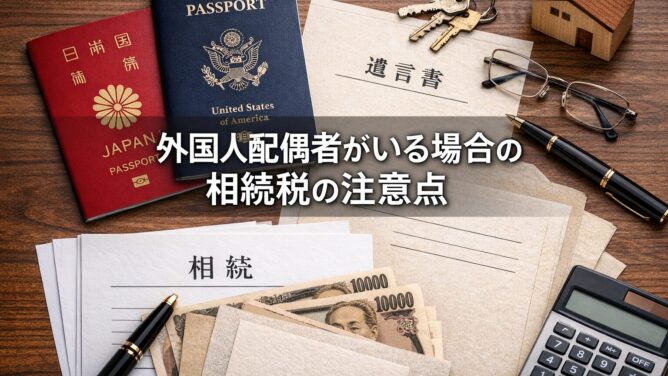
国際相続サポート
【ケース別】外国人配偶者が関わる場合の相続を税理士が解説します
「自分の配偶者は外国人だけど、将来の相続で困ることはないだろうか、、、?」そんなご不安をお持ちですね。 日本在住の日本人(=日本国籍)の方が亡くなり、その日本にある遺産を日本在住の日本人の配偶者が相続する場合、当然に日本の法律に基づいて相続の内容が決まることになります。 しかし、亡くなった方が外国人(=外国籍)である場合や、遺産が外国にある場合は日本の法律に沿っているだけでは相続の内容が決まらないことがあります。 相続は海外の法律が絡むととても複雑になります。そして最悪の場合、遺産を相続できない又は相続するまで長い時間がかかる、ということもあり得ます。 当記事では外国人の配偶者が関わる場合の相続についてケース別に解説します。 自分の場合はどのケースに当てはまるかを把握し、将来の相続に備えましょう。 第1章 相続で外国人の配偶者が関わる場合の基本 まず、被相続人(亡くなった人)が外国人の配偶者である場合と、相続人が外国人の配偶者である場合、それぞれの相続の基本について確認していきましょう。 1-1 被相続人が外国籍の配偶者の場合の相続 まずは被相続人(亡くなった人)が外国籍の配偶者だった場合の相続の基本について確認します。 なお、被相続人(外国籍)、相続人(日本人の配偶者)ともに日本在住の前提とします。 (1)準拠法 被相続人が外国籍の場合、日本の法律に従うと、原則として被相続人の本国法(国籍を持っている国の法律)に基づいて相続の内容(法定相続人や相続分など)が決まることとなります(通則法第36条)。 ただし、例えばその本国の法律が、「不動産は所在地の法律に従うこと」と定めている場合は不動産が所在する国の法律に従うこととなります。この場合結果的に、日本に所在する不動産は日本の法律に基づいて相続の内容(法定相続人や相続分など)が決まることとなります(法律用語ではこれを「反致」と言います)。 また、本国の法律が、「動産は被相続人の生活の本拠地(ドミサイル)の法律に従うこと」と定めている場合は、日本に所在している動産(金融資産等)であっても被相続人の生活の本拠地(ドミサイル)の法律に基づいて相続の内容(法定相続人や相続分など)が決まることとなります。なお、アメリカの各州の相続法ではこのような定めになっていることが多いです。 被相続人の本国法によって取り扱いが異なることとなり、また、本国法によっては被相続人の財産の種類、財産の所在地、生活の本拠地がどこであるかで最終的に従うべき法律が異なることとなります。 実際の具体例を見てみましょう。 【例】 <前提> 被相続人:日本在住(ドミサイルは日本)・アメリカ国籍 相続人:日本在住・日本国籍の配偶者 相続財産:日本に不動産と預金、アメリカに有価証券 <準拠法> この場合、被相続人はアメリカ国籍であるため、本国法であるアメリカの法律(州法)に基づいて法定相続人や法定相続分が決まることとなります。 <日本の不動産の相続> アメリカの法律(州法)では基本的に不動産はその所在地の法律により法定相続人や相続分が決まることとされています。 したがって、被相続人がアメリカ人であっても、日本の不動産に関してはその所在地である日本の法律に基づいて相続することとなります。 <アメリカの有価証券の相続> アメリカの法律(州法)では基本的に動産は生活の本拠地(ドミサイル)に基づいて法定相続人や相続分が決まることとなります。 したがって、被相続人がアメリカ人であっても、有価証券等の動産については被相続人の生活の本拠地(ドミサイル)である日本の法律に基づくこととなります。 ただし、実際の相続手続きについては日本の法律だけでは進められないことが多く、次の(2)②のような実態があります。 (2)実際の相続手続き ①日本国内の財産の相続手続きのポイント 被相続人が外国人の場合、日本国内の財産について日本の法律に従って相続手続きを進められる場合であっても、実際の手続きにあたっては不動産の相続登記や金融機関に提出すべき必要書類が揃わないという問題が生じます。外国人には戸籍がないためです。 被相続人が日本人の場合、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得すれば両親、子ども、配偶者、きょうだいの全てがわかるので、法定相続人が誰か特定することができます。他方、被相続人が外国人でその配偶者が日本人である場合、配偶者の戸籍には結婚の事実等が記載されている可能性もあります。 しかし、それだけでは不十分な内容であることが多いので、戸籍に代わって以下のような書類を集める必要があります。 【戸籍に代わる書類】 ・外国人である被相続人及びその両親、きょうだい等の出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書 等 ・宣誓供述書(相続人が被相続人との関係及び被相続人の法定相続人を確認する内容のもの) ・外国人登録原票、日本における出生届、婚姻届 等(日本に居住する被相続人の場合) なお、これらの書類は外国語で作成されるため、手続きに使用するにあたっては日本語訳を添付する必要があります。 通常、日本にある財産の相続手続きにあたっては以下の書類が必要となります。 ・相続を証明する書類(戸籍) ・住所を証明する書類(住民票等) ・遺産分割協議書と印鑑証明書(遺言がない場合) ②国外の財産の相続手続きのポイント 国外の財産について相続による名義変更手続きを行う場合、準拠法が日本法となる場合においても、実際の名義変更手続きが日本の法律に従って進められるかというとそのようなことはほとんどなく、財産所在地の法律に従わなければ名義変更手続きができないことが通常です。 上記(1)の具体例の場合、アメリカの有価証券を相続するにあたっては、原則としてアメリカでのプロベート手続き(遺産を裁判所の監督のもとで整理・分配する手続き)が必要となり、現地の弁護士や裁判所の関与がなければ解約や名義変更といった相続手続きができないこととなります。 プロベート手続きには相当の時間と専門家に対する費用を要することになります。 【「プロベート手続き」についてはこちらの記事をご参照ください。】 (3)相続税の課税関係 相続税については日本の相続税と国外(本国や財産の所在地)の相続税の両方が課税されることがあり、両国の税制や租税条約を確認する必要があります。 なお、被相続人が外国人の場合も日本の相続税を計算する上での「法定相続人の数」や、「法定相続分」は日本の民法に基づいて判断することとなります。 また、日本の相続税においては「配偶者の税額軽減」という制度があります。 これは、被相続人の配偶者が遺産を相続する場合、一定額まで相続税がかからず、配偶者の税額が軽減される制度です。配偶者の場合、相続する財産が1億6,000万円、もしくは、法定相続分のどちらか多い方までであれば相続税がかかりません。 【「国際相続における日本の相続税」についてはこちらの記事をご参照ください。】 また、両国間の二重課税を防ぐために「外国税額控除」という制度があります。 【「外国税額控除」についてはこちらの記事をご参照ください。】 1-2 相続人が外国籍の配偶者の場合の相続 次に相続人が外国籍の配偶者だった場合の基本について確認します。 なお、被相続人(日本人)、相続人(外国籍の配偶者)ともに日本在住の前提とします。 (1)準拠法 被相続人が日本国籍の場合、被相続人の本国法である日本の法律に基づいて相続の内容(法定相続人や相続分など)が決まることになります。 この場合、相続人の国籍は一切関係ないため、相続人が外国籍であったとしても日本国籍の相続人である場合と同じ整理となります。 (2)実際の相続手続き ①日本国内の財産の相続手続きのポイント 被相続人が日本人である場合、その準拠法は日本の法律となり、日本国内の財産の相続手続きを行う場合には一般的な日本の相続手続きと大きく変わることはありません。 しかし、その相続人である配偶者が外国人である場合、戸籍がないためこれに代わって以下のような書類を集める必要があります。 【戸籍に代わる書類】 ・相続人である外国人の配偶者の出生証明書、婚姻証明書 等 ・宣誓供述書(相続人が被相続人との関係及び被相続人の法定相続人を確認する内容のもの) ・外国人登録原票、日本における出生届、婚姻届 等(日本に居住する相続人の場合) なお、これらの書類は外国語で作成されるため、手続きに使用するにあたっては日本語訳を添付する必要があります。 ②国外の財産の相続手続きのポイント 国外の財産について相続による名義変更手続きを行う場合、準拠法が日本法となる場合においても、実際の手続きは財産所在地の法律に従わなければ進められないことが通常です。 とはいっても、日本人が多く居住する国や地域では、財産の種類、金額によっては現地の裁判所が日本の遺言や遺産分割協議書の効力を認めた、というケースもあるようです。 実際の相続手続きにあたっては国際相続に精通する現地の専門家に確認を行う必要があります。 (3)相続税の課税関係 相続税については日本の相続税と国外(本国や財産の所在地)の相続税の両方が課税されることがあり、両国の税制や租税条約を確認する必要があります。 「配偶者の税額軽減」は配偶者が外国籍だった場合も適用が可能です。 【国際相続における日本の相続税についてはこちらの記事をご参照ください。】 両国間の二重課税を防ぐために「外国税額控除」という制度があります。 【「外国税額控除」についてはこちらの記事をご参照ください。】 第2章 【ケース別】配偶者が外国人の場合の相続のポイント 亡くなった配偶者(被相続人)、または、相続人である配偶者が外国籍であった場合の相続のポイントをまとめると以下のようになります。 なお、被相続人、相続人共に日本在住の前提としています。 ※ 被相続人、相続人ともに日本在住の前提 第3章 配偶者が外国籍の場合の注意点(トラブル防止の対策) 次に配偶者が外国籍である場合の相続における法務と税務の注意点を確認しましょう。 3-1 遺言について 外国籍の配偶者が遺言を作成する場合、一定の条件に当てはまれば日本国内で日本法に従って作成した遺言が有効となります。 しかし、実際に遺言を作成する場合には「財産の所在地ごとに遺言を作成する」のが重要です。財産の所在地以外の国で遺言を作成したとしても、実際の相続が発生した際にその遺言通りに手続きが進められる保証はないためです。 また、財産の所在国によっては遺言が最適な対策とも限らない場合もあります。 そもそも財産を国外に残さないことやトラストやジョイントアカウントなどの対策も含めて最適な方法を検討する必要があります。 3-2 住所・生活の本拠地(ドミサイル)について 当記事は被相続人、相続人ともにその住所・生活の本拠地(ドミサイル)は日本にある前提としました。 被相続人、相続人の双方または片方の住所・生活の本拠地が国外にあれば、準拠法や相続税の課税関係も大きく異なる可能性があることについても留意が必要です。 第4章 国際相続のご相談はマインライフへ 配偶者が外国人で相続の手続きが複雑になるかもしれない・・・。 そのような難しいケースでも、弊社には最適なサポート体制が整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。 年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「配偶者が外国人で相続手続きをどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第5章 まとめ いかがでしたでしょうか。 配偶者が外国人の場合の相続は日本人夫婦の相続とは異なる点が多々ありますが、そのポイントは以下の通りです。 ・原則として被相続人の本国法に基づいて相続の内容(法定相続人や相続分など)が決まる ・ただし、本国法によっては、財産の種類によって財産の所在地や生活の本拠地(ドミサイル)の法律に基づいて相続の内容が決まることもある ・実際の相続手続きは財産の所在地の法律に基づいて進めることが通常。 ・日本で相続手続きを行う場合、外国人については相続を証明する書類として戸籍に代わる宣誓供述書等が必要 ・日本の相続税と国外の相続税がかかる可能性がある ・日本の相続税の計算にあたっては「配偶者の税額軽減」と「外国税額控除」の適用が可能 ・遺言等の相続対策を行うにあたっては複数の方法を含めて慎重な検討が必要 ・配偶者が外国人で相続手続きに不安を感じたら「税理士法人マインライフ」へ! 配偶者が外国人の場合の相続は複数の法律や言語が絡み合いとても複雑なものになります。 スムーズな相続を実現するには生前からの準備・対策を行うことが不可欠です。 相続対策は早く始めれば始めるほど、大きな効果を生みます。 将来の相続に備えて、今できることをひとつずつ着実に行っていきましょう!
国際相続サポート
プロベートとは?仕組み・流れ・回避方法を税理士がわかりやすく解説
「アメリカにある父の遺産、どうやって手続きすればいいの……?」 日本国内の財産でさえ難しい相続手続き。 それが海外の財産となれば、なおさら戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。 実際に調べてみると、目にするのが「プロベート」という聞きなれない言葉。 さらに、英語・法律・制度の壁に加え、時間も費用もかかる手続きと知り、「どうしよう……」と頭を抱えている方も少なくないでしょう。 プロベート手続きは確かに複雑で、財産がある現地の専門家に依頼する必要があります。 そして、日本側でも税金や名義変更などの手続きが関わるため、複数の専門家と連携しながら進める必要があるのが現実です。 だからこそ重要なのが、日本にいながらも全体像を把握し、信頼できる専門家に相談できる体制を整えることです。 本記事では、 ・プロベートとはどのような制度なのか? ・日本と海外の相続手続きの違いは? ・どんな場合にプロベートが必要になるのか? ・プロベートを回避できる方法は? ・プロベート手続きの具体的な流れは? ・現地専門家を選ぶ際の注意点は? ・プロベートが長引く場合の日本の相続税の対応は? といった疑問にお答えしながら、日本にいる相続人が“最初に知っておきたいこと”をわかりやすく解説します。 この記事を読んで、プロベートの制度を正しく理解し、スムーズで正しい相続手続きを行なってください。 第1章 プロベートとは?海外の相続では裁判が必要?? プロベート(Probate)とは、人が亡くなった際に、その遺産を法的に管理・清算し、最終的に相続人へ分配するまでの一連の裁判手続きの制度です。 アメリカやイギリス、オーストラリア、香港、シンガポール、カナダ、ニュージーランド、マレーシアなどの国で採用されている制度です。日本やドイツ、フランスなどの国では原則としてプロベートのような裁判手続きは不要です。 プロベートが不要な日本では、相続人の話し合いにより誰がどの財産を取得するかを決めます。その内容に基づいて、不動産や預金の名義変更などができます。 しかし、プロベートが必要な国では、裁判所の監督のもとで、遺産の確定、債務の弁済、相続人への分配がされます。そのため、多くの費用と時間を要することになります。 1-1 プロベートが必要な理由 プロベートは、亡くなった人の財産をしっかりと整理し安全に引き継ぐために、必要となります。 そのため、裁判所が財産をチェックしていく制度です。 遺言が本物であるか?相続人が正しいか?(本当に相続人か?)借金や税金も適切に整理、清算できているか?といったことなどを裁判所が中立の立場で監督しています。 では、日本の手続きとプロベート手続きが必要なアメリカの相続手続きの比較をしてみましょう。 1-2 日本の相続手続きとの違い/日本とアメリカの比較 日本の相続手続きとプロベート手続きが必要なアメリカの相続手続きには次のような違いがあります。 日本人でもアメリカの法律に従う必要があるのか?という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。次は、その疑問についてお答えします。 1-3 日本人なのにプロベートが必要になるの? 日本人であっても遺産を取得する際に、プロベートの手続きが必要になる場合があります。 日本の法律では、相続は被相続人(亡くなった人)の本国法(日本人であれば日本の法律)によると定められています。しかし、アメリカの多くの州では、不動産が所在する場所の法律を適用すると定められています。 つまり、日本人がアメリカの不動産を所有している場合は、日本の法律では日本の法律が適用されると定めており、アメリカの法律ではアメリカの法律が適用されると定めています。 このように日本とアメリカでどちらの国の法律を適用するか異なることもあります。 実際にこのようなケースではアメリカにある不動産の手続きをするので現地のアメリカの法律により相続手続きをする必要があります。 そして、日本人であってもアメリカに不動産を所有している場合にはプロベートの手続きが必要になります。 日本人でもプロベートの必要があることは分かったけど、どういう場合に必要になるのか?疑問を持たれた方も多いと思います。 基本的にはプロベートのある国に財産があれば必要になりますが、回避する方法もあります。 次の章ではプロベートはどのような場合に回避できるのか?について解説していきます。 第2章 プロベート手続きを回避する5つの方法 プロベートの手続きは費用も時間もかかるため、プロベート手続きを回避する方法がいくつも用意されています。そのうちの5つの方法をご紹介いたします。 ※注意!! いずれの方法も相続が発生する前(ご存命中)に、手を打っておく必要がありますので、注意してください。 2-1 【方法1】死亡時の受取人の指定(POD、TODR、TODD) 不動産や預貯金などの財産について、所有者が死亡した際にその財産を受け取る人をあらかじめ指定しておく方法です。この方法は非常に簡単に行うことができます。 • POD (Payable-on-Death) Accounts: 銀行口座の受取人指定 所有者が死亡した場合の受取人を事前に銀行に申し出ておくものです。 この手続きがされている場合は所有者の死亡後にプロベートを経ずに指定された受取人が受け取ることができます。なお、所有者が存命中は、受取人には権利はなく、所有者は自由に口座を利用・変更・解約できます。 • TODR (Transfer-on-Death Registration): 証券口座の受取人指定 PODと同様に、証券会社や発行会社に所定の用紙を提出するだけで、プロベートを経ずに受取人へ有価証券の所有権を移転することができます。 • TODD (Transfer-on-Death Deed): 不動産における死亡時譲渡証書 不動産の権利証に受取人を指定し、これを法務局に登記することで、プロベートを経ずに受取人へ所有権を移転することができます。所有者はいつでも撤回することが可能で米国などに不動産しか所有していない方に適しています。 ※注意!! TODRやTODDは、口座の種類、証券会社、または州によっては設定ができない場合があります。そのため、事前に金融機関や現地の弁護士に確認が必要です。 受取人に指定した人が先に死亡するケースに備えて、代替の受取人を指定できる場合もあります。 TODDは、国や州によっては居住用不動産に限定されている場合や債務を承継する必要が生じる場合があります。メリットだけでなくデメリットになる場合もありますので指定をする前に現地の弁護士に確認をしておきましょう。 2-2 【方法2】共同所有:残りの生存者へ移転(ジョイント) 複数の人が共同で財産を所有しておくことで、共同所有者のうちの一人が死亡した場合に、その持分が自動的に生存する共同所有者に移転するものです。自動的に移転するためプロベートの手続きが不要となります。 • ジョイント・アカウント (Joint Account) 共同名義の預金口座です。米国の夫婦の預金口座として多く利用され、口座名義人の死亡により、自動的に生存名義人に財産が移転されます。 • ジョイント・テナンシー (Joint Tenancy) 不動産などを共同所有するものです。ジョイント・アカウント同様、共同所有者の一人が死亡した場合にはその死亡した共同所有者の持分が生存する他の共同所有者に自動的に移転・帰属します。 ※注意!! • 共同所有者全員が亡くなるとプロベートが必要となります!! • ジョイントにする際に贈与税注意!! 不動産などをジョイントにする際に、資金を拠出していない人が名義人として加わる場合には、日本では資金を拠出した人からの贈与とみなされ、贈与税が発生します。 2-3 【方法3】生前信託(Living Trust) 日本にも同様の制度がありますが、信託制度を活用する方法です。 信託とは、財産を所有している人が信頼できる第三者に、持っている財産の運用や管理、最終的な処分まで任せるものです。そして、どのように運用、管理、処分などをするのかについてあらかじめ契約で定めておきます。その契約で、自分が死亡した時はこの人に財産を渡すということを定めておけばプロベートを経ずに財産を移転することができます。 ※注意!! • 日本の財産は一緒に信託財産として管理などができない場合があります。 • 受託者になる要件として米国非居住者は、基本的に米国で生前信託の受託者になることはできません。 • 信託の設定には多くの手間や費用がかかります。 • 一度信託を設定した後も、新たに財産を取得した場合などは、それらも想定して信託や遺言を設定しておくか、その都度変更しなければ、新たに取得した財産についてプロベートを回避することができません。 2-4 【方法4】日本法人による間接保有 日本の法人が海外財産を保有する方法です。法人が保有している場合は、個人の相続手続きであるプロベートは必要なくなります。個人が所有するのは日本の法人の株式となるため、日本国内の他の財産と同じように相続手続きをすることができます。 ※注意!! 法人の設立や法人への資産の移管に伴う複雑な税務や法務の検討が必要となります。 法人へ資産を移管する際に、所得税や贈与税などが発生する場合があります。 2-5 【方法5】少額資産 遺産の総額が一定額以下の場合には、プロベート手続きが不要または簡略化される場合があります。 ※注意!! 少額であるかについては、国や地域、金融機関などによって大きく異なります。 なお、受取人が指定されている生命保険金や退職年金は、プロベートの対象になりません。 また、その国の遺言書を作成している場合でもプロベート手続きは必要となり遺言書の内容は裁判所を通じて検認され執行されます。遺言書は亡くなった方の意思を明確にする重要な書類になり、遺言で指定された遺言執行者がプロベートの手続を行うことになります。 次章では、プロベートの具体的な手続きの流れについてご説明します。 第3章 プロベートを進めていく具体的な流れ この章ではプロベートの手続きが必要になってしまった場合、どのような流れで手続きが進むのか解説していきます。 プロベートの手続きの6つのStep 【Step1】 相続の発生とプロベートの申立 人が死亡すると相続が開始します。 遺言がある場合は、まずその遺言書を裁判所に提出して有効かどうかをチェックしてもらいます。 遺言がない場合は、裁判所が「誰が遺産を管理するか(遺産管理人)」を決めます。 【Step2】 遺言執行者又は遺産管理人が正式に任命される 遺言で指定されていた遺言執行者(遺言に書かれた内容を故人に代わって実行する人)や裁判所が選んだ遺産管理人が手続きの責任者となります。 裁判所から管理をする『許可書』が発行されます。 【Step3】 財産や借金を調査し目録(リスト)を作成 故人が持っていた財産(預金・不動産・株など)や借金や税金をすべて調べてリストを作成します。 このリストは裁判所に提出し、その後の手続きのベースになります。 【Step4】 債務・税金の清算 財産の中から、遺言執行者や遺産管理人の報酬、故人の借金や未払の税金などを優先して支払います。そのため、日本のように相続人が個人的に借金を引き継ぐことは基本的にありません。 【Step5】 財産の分配 債務や税金の清算後、残った財産を相続人に分配します。 遺言がある場合→遺言に書かれた内容に従って分配されます。 遺言がない場合→各州の法律に従って相続人に分配されます。 【Step6】 裁判所への完了報告 全ての手続きが完了した後、その旨を裁判所に報告しプロベートは終了となります。 ~プロベートの4つのデメリット~ 1 期間が長期間:プロベートの手続きは半年から3年かかることもあります。 2 費用が高額:裁判所に支払う費用、鑑定費用、弁護士費用などが発生し、高額になることがあります。特に、プロベート対象財産が少額であっても、多額の費用や時間がかかり、コスト倒れになることが多々あります。 3 プライバシーの問題:手続きの中で遺言書の内容や遺産の内訳が公開され、プライバシーを確保することができません。 4 国際相続の複雑さ:国際相続の場合、日本の戸籍謄本などの書類は翻訳の上翻訳証明を付けることが多く、別途、海外の公的書類(出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書など)や宣誓供述書などを集める必要があります。これらの書類は、アポスティーユ認証または領事認証が必要となる場合があります。また、遺言書や遺産分割協議書が外国語で記載されている場合、翻訳が必要となることもあります。 なお、プロベートの手続きは裁判手続きのため現地の弁護士に依頼するのが通常です。現地の弁護士を選ぶ際の注意点について次章で詳しく解説します。 第4章 現地の専門家を選ぶ際の4つのPoint 現地の制度や相場を理解し、日本と現地の専門家が連携できる体制を作ることが、海外相続をスムーズに進める最大のポイントです。特に、日本の専門家を経由して現地の専門家を探すことで手間やリスクを大きく減らせます。 Point 1 日本の専門家に紹介を受けるのが一番のPoint 日本の専門家に紹介を受けるのが一番スムーズに進みます。この後の3つのPointもケアしてもらえます。 自分で現地の専門家を探すのは難しく、報酬や支払いタイミングの交渉も容易ではありません。相場感がないまま契約すると、通常より高い額になるリスクもあります。 国際相続に精通した日本の専門家(税理士や弁護士)であれば、現地の信頼できる専門家とネットワークを持っていることが多く、このようなリスクも軽減できます。また、日本の税務も必要な場合は、一緒に依頼できるメリットもあります。 Point 2 州ごとに法律や手続きが違うので適用する法律に精通した専門家を探す アメリカは州ごとに法律が違います。 どの州の法律が適用されるのか確認し、その州に精通した専門家を選ぶことが必要です。 カリフォルニア州の法律に基づいて手続きが必要なのにニューヨーク州専門の弁護士に依頼してしまうとスムーズに手続きが進まないことがあります。 Point 3 報酬形態と相場を必ず確認する 現地専門家の報酬は、日本の専門家よりも高額になることが多いです。 それでも、現地での相場として高額なのか妥当なのかについては検討をする必要があります。 なお、主な報酬形態は『遺産総額の○%(例:2〜5%)』『タイムチャージ制(時間あたり○ドル)』のいずれかです。 Point 4 報酬を支払うタイミングを確認する プロベートの手続きは長期間になります。 この間、遺産は裁判所の管理下にあり、自由に使ったり名義変更したりできません。 そのため、費用を一時的に相続人が立て替える必要が生じる場合があります。 契約によっては、報酬の一部を名義変更完了後に支払うことも可能です。支払時期によって相続人の資金負担が大きく変わるので注意が必要です。 現地の専門家選びは、費用や期間だけでなく、日本での税務との連携も欠かせません。 次の章では、日本の税務の注意点を取り上げます。 第5章 プロベートが終わっていなくても日本の相続税は待ってくれない プロベートにどれだけ時間がかかっても、日本の相続税の期限は延びません。 日本の相続税の期限は「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内」です。この期限内に相続税の申告と納税をする必要があります。 亡くなった方と相続人のいずれかでも日本に在住している場合、基本的に海外の財産も含めて日本の相続税の対象になります。 プロベート手続きが間に合わない場合は財産の分割が完了していないもの(未分割)として一度申告し納税をすることになります。 その後、プロベート手続きが完了し財産の分配が行われた後、必要に応じて申告書を修正し提出することになります。 なお、日本の相続税には各種特例が設けられておりますが、未分割の場合には適用できないものがあります。そのため、プロベート手続きが間に合わない場合にはそれらの特例を受けずに申告することになります。 第6章 海外に財産があり、お困りの場合はぜひ税理士法人マインライフへご相談ください 財産が海外にあり、プロベートの手続きが必要かもしれない・・・。 そのような難しいケースでも、最適なサポート体制が弊社には整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「海外の財産をどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第7章 まとめ いかがだったでしょうか。 相続が発生した時、海外に財産がある場合はプロベートという制度の適用を受けなければならなくなります。 プロベート制度のまとめ ・プロベートは、亡くなった人の財産を法的に整理・清算し、相続人へ分配するための裁判手続き ・アメリカなどに不動産や口座がある場合、日本人でもプロベートが必要になる ・プロベートは時間も費用もかかるが、回避できる方法(受取人指定、共同所有、生前信託など)もある ・回避できない場合は6つのステップで進行する(遺言提出~完了報告) ・デメリットは長期化・高額費用・情報公開・国際書類の煩雑さ ・現地の専門家選びは、日本の専門家経由が最も安全でスムーズ ・日本の相続税は、プロベートが終わらなくても10か月以内に申告・納税が必要 プロベートは手続きが煩雑で、時間も費用も想像以上にかかるものです。 まずは信頼できる日本の専門家に相談し、現地との橋渡しをしてもらうことから始めましょう。
国際相続サポート
国際相続は誰に相談すべきか?失敗しないポイント
「相続人の一人が海外に住んでいる」又は「海外に財産がある」そんな時にまず誰に相談したらいいのか? おそらく今記事を読んでいる方もそのような悩みがあるのかと思います。 結論としては、最初の相談窓口は“国際相続に強い税理士法人”が最適といえます。 なぜなら、国境をまたぐ相続は二重課税・手続の壁が大きく、国際相続に強い税理士法人なら評価・翻訳・期限管理までサポートし、現地専門家と連携して無駄な税負担と手戻りを防げるからです。 国際相続に精通した税理士が全体像(税務・法務・登記・海外手続)を設計し、必要に応じて税理士・弁護士・司法書士・海外弁護士や公認会計士などをチームにして進めるのが、最短かつ安全な進め方です。 申告期限や海外手続は待ってくれません—この記事を読んで「相談してみよう」と思っていただければ幸いです。 第1章 国際相続は専門家に相談すべき 国際相続の場合の結論としては「迷わず専門家へ相談すべき」です。 海外がからむ相続は、日本だけの手続きでは完結しないことが多く、準備の遅れがそのまま負担やリスクに直結します。 最初から国際相続に強い専門家に相談するのがいちばん安心で早い進め方です。 【なぜ専門家が必要なのか】 ①手続きが「日本+海外」で二重になるから 海外がからむ相続の場合、日本国内の手続きとは別に海外での手続きが必要となります。 例えば、アメリカに証券口座がある場合、日本では相続税の申告、アメリカ側では口座名義を変える手続きや裁判所を通す手続き(プロベート)が必要になることがあります。 ※プロベート=遺産の内容や相続人を裁判所の管理下で確認・整理する手続きです。 ②税金の判断ミスがコスト増につながるから 海外がからむ相続の場合、税務手続きだけをとっても非常に複雑になることが多いです。 海外の財産の評価方法、日本の相続税の申告、外国で払った税金の精算(外国税額控除)など、判断を誤ると税金が増えたり、期限に遅れて加算税がかかったりします。 ・必要書類の準備に時間がかかるから 海外がからむ相続の場合、まず書類をそろえることが最大のポイントで、準備に最も労力を要します。 戸籍の収集、翻訳、海外提出のための認証手続きなど、取り寄せに数週間〜数か月かかることも珍しくありません。 早く動くほど有利です。 第2章 【ケース別】誰に相談するといいか 相続は専門家ごとに守備範囲が異なります。 税務(評価・申告・納税設計)は税理士、紛争や契約・準拠法は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、海外の裁判所手続(プロベート)や現地金融機関対応は海外弁護士——それぞれ役割が分かれています。 この章では複雑な国際相続において、「相談時期」・「相談内容」に応じて誰に相談すべきか解説いたします。 ただし、専門家だからといって皆が国際相続に精通しているわけではありません。 最も安心かつ安全なのは、「国際相続に精通している専門家に依頼すること」です。 専門家選びを間違えると、二度手間、三度手間になる可能性もあります。 2-1. 相続開始「前」:生前の準備 相談内容 まず相談する専門家 主なサポート 生前の相続税対策など、税金に関わること 税理士 ・相続税の試算 ・財産評価・節税設計 ・納税資金計画 ・二次相続の見通し プロベート対策など、法務手続きに関わること 弁護士 ・遺言・信託の法的設計 ・準拠法の検討 ・将来紛争の予防 ・各国の法務要件の確認 基本的には税金に係わることは税理士、名義変更等の手続き関係に係わることは弁護士にご相談いただければ大丈夫です。 2-2. 相続開始「後」:発生後の対応 相談内容(発生後) まず相談する専門家 主なサポート 海外に財産がある 税理士(国際相続) ※必要に応じ海外弁護士 ・日本の相続税申告・評価 ・海外での名義変更やプロベート要否の判断 ・金融機関・現地専門家との連携 ・翻訳・認証の段取り 相続人が海外在住 or 外国籍 税理士+司法書士 ・署名証明・領事認証・アポスティーユの要否判断 ・本人確認書類の整合(氏名表記ゆれ等) ・相続登記・銀行手続の要件整理 被相続人が外国籍 税理士(国際相続) ※必要に応じ弁護士 ・課税範囲の確認(居住歴・国籍等) ・準拠法の整理 ・日本申告と各国手続の並走管理 ・必要書類の翻訳・認証手配 手続きの中でも最も優先すべきは相続税申告になります。 なぜなら、申告手続きには明確な期限があり期限を過ぎてしまうとペナルティがあるからです。 したがって、ご相続が発生した場合にはまず税理士にご相談いただくのが最も安心な方法だと思います。 2-3. まずは無料相談する 悩んだらまずは無料相談してみるのがいいでしょう。 海外がからむ相続の場合、必要な手続きや書類はケースによって様々です。 そこで、国際的なネットワークがあるかどうか、実績が豊富かどうか、海外の法律に詳しいかどうか、料金が明確か、フットワークが軽そうか、自分との相性を見てみましょう。 迷ったら:税理士法人マインライフにご相談ください。 全体像を整理し、必要に応じて各専門家へおつなぎします。 第3章 相談を始める前に準備しておくべきこと 「税理士に何をどう相談すればいいのか分からない」という方も多いかと思います。 この章では、ご相談前にご準備いただくとスムーズに進むポイントを、分かりやすくご案内します。 3-1. 相談内容はどんな内容でも大丈夫 海外がからむ相続のことなら、内容があいまいでも大丈夫です。 最初から論点をきれいに整理できている方は多くありません。 ・相続税のこと ・不動産の相続登記 ・海外で必要な手続き(プロベート等) ・遺言・信託の扱い ・口座や名義の変更 ・書類の翻訳・認証(アポスティーユ等) など、気になっていることをそのまま伝えてください。専門家が全体像を整理し、必要な手順を一緒に決めていきます。 相続の手続きは申告期限まで長い付き合いになります。 初回相談では、話しやすいか・説明がわかりやすいか・自分に合うかもチェックして、安心して任せられる税理士を選びましょう。 3-2 準備するもの 一般的には下記のような書類をご準備いただけるといいかと思います。 ☑ 財産がわかる資料(通帳・残高証明、証券明細、保険証券のコピー など) ☑ 家族関係がわかる書類(戸籍一式/家族関係図でも可) その他必要なものがないか、面談の予約時にご確認いただけるといいかと思います。 【税理士法人マインライフにご相談いただく場合】 ① 事前にメモしておいてほしいこと ☑亡くなった日 ☑財産の全体像(何があるか・どこにあるか・名義・だいたいの金額) ☑住んでいた国/国籍(故人・相続人) ☑海外での手続きの進み具合(現地の相続手続きが進んでいるか など) ☑その他(遺言の有無、信託、贈与、保険、共同名義 など) ② 面談当日にあると助かるもの(そろう範囲でOK) ☑財産がわかるもの(通帳・残高証明、証券の明細、保険証券のコピー など) ☑家族関係がわかるもの(戸籍や家族関係図 など) ☑日本に不動産がある場合:固定資産税の課税明細、登記簿 など ☑遺言・信託の書類(あれば) ☑海外とのやり取りの控え(現地の弁護士・会計士の連絡先やメール など) ☑本人確認書類(運転免許証など)と連絡先 すべて完璧にそろっていなくて大丈夫です。わかる範囲でお持ちください。 必要なものは面談で一緒に整理し、集め方もこちらでご案内します。 3-3. 費用の目安 国際相続は複雑な案件が多いため、費用については案件によって変動するとされていることが多いです。 なので、明確な金額の提示がなく作業が進んでから報酬の提示を受けることになることも少なくないようです。 専門家に依頼する際には必ず報酬について確認するようにしましょう。 【税理士法人マインライフにご相談いただく場合】 税理士法人マインライフでは、報酬規程を設けるとともに初回相談は無料で行っています。 ※簡易的な報酬表になりますので詳しくは下記の弊社ホームページをご確認ください。 https://www.mine-life.jp/service/international-inheritance-support また、ヒアリング後に業務範囲・スケジュール・お見積書を提示し、ご同意いただいた後に着手します。 追加報酬が生じる場合には、事前にご説明したうえで再度お見積りをさせていただきますのでご安心ください。 第4章 相談事例 下記は、実際に私たちにご相談いただいた案件をベースに、状況・対応・結果・学びの順で整理した事例です。 ※個人が特定されない範囲で再構成しています。 相談すべきかお悩みになっている方の参考になれば幸いです。 事例A|相続人の一人が海外在住だったケース 【状況】 相続が起きたタイミングで、お子さまの一人がちょうど海外赴任中。財産は日本だけ、遺言はなし。なので、遺産分割協議が必要でした。 【対応】 海外にいる相続人の署名証明(署名の本物確認)と在留証明を、現地の大使館や役所で取ってもらいました。 日本側では協議書の案を用意して、翻訳が必要かもチェック。 時差や郵送時間を見込みつつ、申告期限(10か月)から逆算してスケジュールを立てました。 【結果】 書類の取り寄せに時間はかかったものの、期限内に協議成立→申告まで完了しました。 【ポイント】 海外の手続きは予約・郵送で思ったより時間がかかることが多いです。できるだけ早めに着手しましょう。 事例B|被相続人が外国籍で、海外にも財産があったケース 【状況】 被相続人は外国籍で日本に居住。財産は日本と海外の両方にありました。 【対応】 日本側は当法人で評価と申告の設計、必要書類の整理、期限管理を担当することになりました。 海外側は、提携の日本の弁護士と現地の弁護士で連携して、プロベート(裁判所の手続き)や名義変更・換金を進めました。 日本の申告に必要な海外資産の評価額・基準日を早めに固めるため、海外の進行と並走しました。 【結果】 海外の名義変更・換金と日本の申告を同時並行で無事完了。 【ポイント】 プロベートは現地弁護士との連携が必須です。 日本の申告でも海外資産の評価額が必要なので、海外手続きは早めにスタートが鉄則です。 事例C|海外在住のお母さまの財産について、生前対策のご相談 【状況】 お母さまは海外在住で預金が多め。相続人の子どもは日本在住で、「日本の相続税が心配…」というご相談でした。 【対応】 まず前提を確認。一般論として、相続人が日本居住だと海外の財産も課税対象になり得ます。 「子どもが海外移住して、相続の10年以上前から海外居住なら日本課税を外れる可能性がある」――という理屈上の選択肢もお伝えしましたが、仕事や家族の事情を考えると現実的ではなし。 そこで、生前贈与の活用や資産配分の見直しなど、無理のない対策に切り替え。 さらに手続き面の負担を減らすため、現地の弁護士とリビングトラスト(生前信託)を作成してもらいました。 【結果】 税金はできる範囲での軽減策になりました。 手続きはトラストを用いてシンプル化しました。家族の暮らしを大きく変えず、コストと効果のバランスをとった形で落ち着きました。 【ポイント】 相続税の“劇的な対策”は、年齢・居住地・家族事情によっては難しいこともあります。 でも早めに相談すれば、選べる手段は確実に増えます。 第5章 国際相続は税理士法人マインライフへ 国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑で、専門家の存在が成功の分かれ道となります。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」―― そのようなときは、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 最初の一歩を踏み出すことが、複雑な国際相続を解決へ導く最大のカギとなります。 第6章 まとめ いかがだったでしょうか。 今回のコラムでは、国際相続では専門家ごとに守備範囲が異なること、そして最初の相談窓口として“国際相続に精通した税理士法人又は弁護士法人”を起点にするのが安全かつ最短であることをお伝えしました。 税務(評価・申告・納税設計)と、法務・登記・海外プロベート等の複数の手続を一枚の設計図で並走させ、必要に応じて税理士・弁護士・司法書士・海外弁護士にバトンをつなぐ体制づくりが重要です。 さらに、国際相続の手続きには時間がかかるため、早めの準備が成否を左右します。 特に、次のような点が重要です。 ・まずは国際相続に精通した専門家を起点に:全体設計(論点・担当・スケジュール)を作り、連携先専門家を適切に紹介・調整できる窓口を選ぶ ・相談のハードルは低く:テーマが曖昧でもOK。「あるものだけ」で持参し、不足は必要書類リストで埋める ・費用は事前に提示してくれる専門家を選ぶ:初回無料相談等で費用も確認できるといいでしょう つまり、「誰でもよいから相談」ではなく、国際相続の実務に慣れ、他士業と連携できる税理士法人を最初の窓口に選ぶことが、期限遅延・手戻り・過大コストを避ける近道です。 相続や海外資産の整理を検討し始めた段階から、どうぞ早めにご相談ください。 最初の一歩(全体像の把握と期限逆算)が、その後の負担を大きく減らします。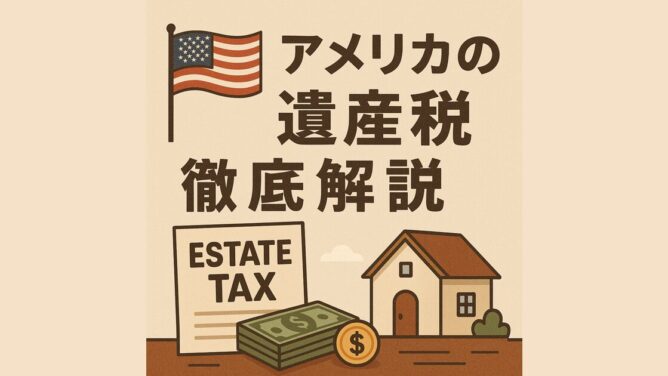
国際相続サポート
【2026年最新版】アメリカの相続税(遺産税)を徹底解説|日本との違い・二重課税の防ぎ方【プロが解説】
「アメリカにある財産にアメリカの相続税はかかるのだろうか。」そんなお悩みをお持ちですね。 結論、日本人の場合はほとんどのケースでアメリカの相続税(連邦税としての遺産税)はかからない、というのが実情です。 しかし、アメリカの相続税のルールは日本の相続税のルールとは全く異なります。 もし、アメリカの相続税の申告・納税義務があるにも関わらずこれを怠ると、ペナルティの対象となるため、正確な対応が求められます。 また、税金には申告・納税の期限があります。海外の税金については知らずにこの期限を過ぎてしまい、その対応に時間的にも金銭的にも苦労を強いられるケースが多いのが現実です。 当記事を通して、読者の皆様にアメリカの相続税のルールについて知っていただき、ご自身にアメリカの相続税はかかるのか、また、どのように対応すべきかの判断をする際の一助となれば幸いです。 アメリカの相続税を知り、事前の対処をしていきましょう! 【当記事は2026年1月1日時点の法令に基づき作成しております。】 1章 アメリカの相続税(遺産税)の基本知識 アメリカには相続に関する連邦税として「遺産税」があります。 この遺産税は日本の相続税とは異なり、財産を渡す側である被相続人(亡くなった人)が納税義務者とされています。また、アメリカ市民・アメリカ居住者であるか、アメリカ非居住者であるかにより税金の取扱いが異なります。また、州によっては州税としての遺産税(相続税)が存在します。 1-1 日米の相続税の違い 日本とアメリカの相続税の違いで最も大きなものはその基礎控除額の大きさでしょう。 日本の相続税の基礎控除が3,000万円からであるのに対して、アメリカの連邦遺産税の基礎控除額(2026年分)は1,500万ドルで1ドル150円の為替レートで換算すると22.5億円となります。 以下に日本の相続税とアメリカの遺産税との違いを表にまとめました。 ※ 被相続人が日本人の場合には日米相続税条約による特例計算あり ※ アメリカの遺産税の基礎控除額は頻繁に改正されるため注意が必要 1-2 基礎控除額 2026年現在、被相続人がアメリカ市民またはアメリカ居住者の場合のアメリカ遺産税の基礎控除額は1,500万ドルとなっています。また、被相続人がアメリカ非居住者の場合の基礎控除額は6万ドルとなっており、両者には大きな差があります。 日米相続税条約の適用により、被相続人がアメリカ非居住者であったとしても日本人である場合には、アメリカ市民、アメリカ居住者の場合の基礎控除額(2026年は1,500万ドル)を基準とした特例計算が認められています。 具体的には、被相続人の遺産総額のうちアメリカの財産の占める割合に応じた基礎控除額が適用できます。 したがって、被相続人が日本人の場合にはほとんどのケースでアメリカの連邦遺産税は課税されない、というのが実態となります。 なお、このアメリカ遺産税の基礎控除額は毎年のように改正が行われており、実際に遺産税の計算をする際にはその年の基礎控除額の確認が必須となります。 1-3 税率の仕組み(累進課税) 財産が基礎控除額を超えた場合、遺産税が発生することとなり、各種控除後の遺産の金額に税率をかけて遺産税を算出する仕組みとなります。 アメリカの遺産税の税率は以下の表のとおり累進税率となっています。 課税の対象となる遺産が大きくなるほど税率が高くなる仕組みとなっています。 アメリカ遺産税 税率表 最高税率は40%と日本の相続税の最高税率55%よりも低い税率となっています。 1-4 州税として遺産税 アメリカには、連邦税としての遺産税の他に州によっては州税としての遺産税(相続税)が存在します。 例を挙げると、 ・ニューヨーク州 → 遺産税が課される ・ペンシルバニア州 → 相続税が課される ・カリフォルニア州 → 遺産税も相続税も課されない など、課税の有無や方法は州ごとにさまざまです。 連邦税の遺産税はかからない場合でも州税としての遺産税(相続税)はかかる、といった場合もあります。 財産が所在する州の遺産税(相続税)のルールについてもしっかりと確認をする必要があります。 2章 アメリカの遺産税の手続きの流れ アメリカの遺産税の計算、納税までのプロセスは日本とは異なり、特殊な手続きが必要となります。 2-1 プロベート手続きが求められる アメリカの遺産税の計算、納税はプロベートという一連の手続きの中で行われます。 プロベートとは、人が亡くなった際に、その遺産を法的に管理・清算し、最終的に相続人へ分配するまでの一連の裁判手続きのことです。 プロベート手続きは、ある意味遺産税よりもやっかいです。 プロベートが不要な日本では、相続人の話し合いにより誰がどの財産を取得するかを決めます。その内容に基づいて、不動産や預金の名義変更などができます。 しかし、プロベートが必要なアメリカでは、裁判所の監督のもとで、遺産の確定、債務・税金の清算、相続人への分配がされます。そのため、多くの費用(裁判所費用・弁護士費用)と時間(数か月~1年以上)を要することになります。 現実には、アメリカの遺産税はかからないがプロベート手続きは必要になる、というケースが数多くあります。 【「プロベート手続き」についてはこちらの記事をご参照ください】 2-2 申告に必要な書類と提出先・申告納税期限 アメリカで提出する遺産税の申告書とその提出期限等は被相続人の区分に応じて以下のようになっています。 注意すべきは申告・納税期限が被相続人の死亡後9か月以内となっている点で、日本の相続税の申告納税期限である10か月以内よりも短くなっています。事前の手続きにより期限の延長申請を行うことも可能ですので、早めからの対応が肝心です。 また、納税が生じない場合であっても、以下に該当する場合にはIRS(アメリカ合衆国内国歳入庁、日本の国税庁にあたる機関。)や米国財務省への報告義務が生じます。 3章 アメリカの遺産税を軽減するための対策 これまで見てきたようにアメリカの遺産税とプロベート手続きはとても複雑ですが、この負担を軽減する具体策について確認していきましょう。 3-1 財産を日本へ移す アメリカの遺産税を回避するために最も有効な手段は、財産をアメリカ国外へ移すことです。 アメリカ非居住者である場合、アメリカの遺産税の対象となるのはアメリカ国内の財産のみとなります。 したがって、アメリカ非居住者がアメリカにある財産を全て日本に移せばアメリカの遺産税の心配はなくなることとなります。 また、アメリカに財産はなくなりますので将来のプロベート手続きの心配も無くなります。 3-2 アメリカでの生前贈与 アメリカ非居住者がアメリカにある預金(無形資産)を贈与した場合、アメリカの贈与税はかからないこととなっています。 なお、贈与者が日本人で日本在住である場合等一定の場合には日本の贈与税が発生することとなるので、この点については留意が必要です。 また、贈与したアメリカの財産はご本人の財産でなくなりますので、将来のプロベート手続きの心配はいらないこととなります。 3-3 トラスト(信託)やジョイント(共同所有)の活用 遺産税の対策ではありませんが、アメリカにある財産をトラスト(信託)やジョイント(共同所有)にすることは、プロベート手続きを回避する有効な手段となります。 トラスト(信託)とは、財産を所有している人が信託契約によって信頼できる第三者に持っている財産の運用や管理、最終的な処分までを任せるものです。その契約おいて自分が死亡した時はこの人に財産を渡す、ということを定めておけばプロベートを経ずに財産を移転することができます。 また、ジョイント(共同所有)とは、財産を共同所有にすることです。共同所有者が亡くなった場合にその所有権が残りの共同所有者に移転するため、プロベート手続きが不要となります。代表的なものとしてジョイント・アカウント(共同名義の預金口座)とジョイント・テナンシー(不動産の共同所有)があります。 4章 アメリカの遺産税でよくある注意点 アメリカの遺産税を考える上では日本の相続税だけを考えるだけの場合とは異なる注意点があります。 4-1 日本の相続税との二重課税のリスク アメリカにある財産に対して、日本の相続税とアメリカの遺産税の両方がかかってしまう二重課税のリスクがあります。 当記事を見ていただいている多くの方が該当すると思われる「被相続人(亡くなった人)が日本人で10年以内に日本住んでいたことがあるケース」の場合、日本国外の財産を含む全ての財産に対して日本の相続税がかかることとなります。アメリカに財産があった場合、この財産は日本の相続税の対象となり、かつ、アメリカの遺産税の対象にもなる、ということになります。 この複数カ国による二重課税を排除するために「外国税額控除」という制度があります。 【例】 前提:日本に住んでいる方が、日本に20億円の財産、アメリカに20億円の財産がある状態で亡くなった。相続人は日本に住んでいる子ども1人。 日本の相続税:全世界の財産(40億円)に対して日本の相続税20億円が発生 アメリカの相続税:アメリカにある財産(20億円)に対してアメリカの遺産税4億円が発生 この場合、全世界の財産にかかる日本の相続税20億円から、外国税額控除によってアメリカの遺産税4億円を差し引き、残りの16億円だけを納めることとなります。 なお、実務上は日本の相続税の申告期限(原則被相続人が亡くなってから10ヶ月以内)までにアメリカの遺産税が確定しないことが多いです。 その場合、日本の相続税の申告期限までに一旦20億円を納税します。 そして、アメリカの遺産税4億円が確定次第、当該4億円の外国税額控除を適用した申告書を再提出(更正の請求手続き)し、4億円の還付を受けることとなります。 4-2 円転時の為替差益の落とし穴 相続した外貨(米ドル)を円に換えたときの税金について注意が必要です。 日本在住の相続人が相続した外貨(米ドル)を円に換えた場合、その金額が、相続開始日(被相続人が亡くなった日)時点の相続税評価額(相続開始日時点のドルベースの残高×相続開始日のTTBレート)よりも大きい場合は、その差額が為替差益として所得税・住民税の対象となります。 この為替差益は雑所得として、所得税計算上の総合課税(累進税率)の対象となり、その所得税・住民税率は合わせて最大約55%となります。 日本の相続税の納税が必要となった場合、日本円での納税が必要となりますので、これに伴って外貨を円転した場合には注意が必要です。 4-3 相続したアメリカの不動産を売却したとき 日本に住む相続人が、アメリカの不動産を売却した場合、その売却益(譲渡所得)の計算は以下のようになります。 不動産の売却益(譲渡所得)の計算 譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除額(適用がある場合)=譲渡所得 相続したアメリカの不動産を相続後すぐに売却した場合、アメリカの所得税は結果的に発生しないことが多いです。 これは、日本の譲渡所得計算上の取得費は被相続人の取得費をそのまま引き継ぐのに対し、アメリカの譲渡所得計算上の取得費は被相続人の死亡日の時価となるためです。 つまり、死亡日の時価(取得費)と売却時点の時価(売却額)が同額であれば譲渡益は生じないこととなります。 ただし、日本居住者がアメリカの不動産を売却する場合は買主によってアメリカの所得税が源泉徴収され、この税金の還付を受けるにはアメリカでの確定申告が必要となるので留意が必要です。 5章 専門家への依頼について アメリカの遺産税への対応を考える上では専門家の協力を得ることが重要です。 次に、いつ、誰に、どのように依頼すべきかを整理します。 5-1 いつ専門家に依頼すべきか 結論、アメリカに財産がありその相続に備える場合、すぐにでも相談すべき、ということになります。 アメリカの遺産税(と日本の相続税)については、財産をお持ちの方が亡くなってからできる対策はほとんどありません。万が一があってからでは遅いのです。 遺産税の節税やプロベート対策を行うならば、生前の対策が必須となります。 5-2 誰に依頼するべきか(弁護士・税理士・CPA) 国際相続に精通した日本の専門家(税理士や弁護士)に依頼すべきです。 日本にお住いの方のアメリカの遺産税、相続対策を検討する上ではアメリカの法律だけでなく、日本の法律についても精通している必要があります。両者は密接に関わり合うためです。 また、トラストの設定などアメリカ現地の専門家のサポートが必要となった場合、自分で現地の専門家を探すのは難しく、報酬や支払いタイミングの交渉も容易ではありません。相場感がないまま契約すると、通常より高い金額になるリスクもあります。 国際相続に精通した日本の専門家(税理士や弁護士)であれば、現地の信頼できる専門家とネットワークを持っていることが多く、このようなリスクも軽減できます。 5-3 依頼するときに必要な情報 相談する際は、以下の情報があれば専門家においてスムースな対応が可能となります。 ・ご自身の国籍、居住歴、財産に関する情報 ・ご相続人様の人数、続柄、国籍、ご年齢、居住歴の情報 ・今後のライフプラン ・資産承継のご意向 相続対策はご本人の状況に応じたオーダーメイドのプランニングをすべきものとなります。 5-4 費用の目安 遺産税が発生する場合のアメリカの専門家の報酬は、日本の専門家よりも高額になることが多いです。 主な報酬形態は「遺産総額の○%(例:2〜5%)」、「タイムチャージ制(時間あたり○ドル)」のいずれかです。 提示された報酬額が現地の相場として高額なのか妥当なのかについては検討をする必要があります。 海外の専門家から相場よりもずっと高い報酬の提示を受けたり、実際に契約をした後に連絡がない(レスポンスが非常に悪い)、というのはよくあるトラブルです。 通常、日本の信頼できる専門家からのアメリカの専門家の紹介を受ければそのような心配は少なくなります。なぜならば、そのようなアメリカの専門家は紹介元である日本の専門家と普段から一緒に仕事をしており、その実績に基づいて安心して仕事を任せられることが通常であるからです。 6章 アメリカに財産があり、お困りの場合はぜひ税理士法人マインライフへご相談ください アメリカに財産があり、アメリカの遺産税やプロベート対策が必要かもしれない・・・。 そのような難しいケースでも、弊社には最適なサポート体制が整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。 年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「アメリカの財産をどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 7章 まとめ いかがでしたでしょうか。 アメリカの遺産税の制度には日本の相続税とは異なる点が多々ありますがそのポイントは以下の通りです。 ・日本人の場合はアメリカの連邦遺産税はかからないことが多い(日米相続税条約により基礎控除が多額となるため) ・アメリカの連邦税としての遺産税はかからなくとも、州税としての遺産税がかかることがあるので注意が必要 ・アメリカの遺産税の申告・納税期限は亡くなってから9ヶ月以内(延長制度あり) ・通常、アメリカの財産を相続する場合はプロベート手続きが必要となり、コストと時間がかかる ・遺産税対策やプロベート対策としてアメリカにある財産を日本へ移すことは有効 ・アメリカの遺産税・プロベート対策は早期に国際相続に精通した日本の専門家(税理士や弁護士)に相談した方が良い ・外国税額控除(二重課税の排除)や円転時の為替差損益等、国際相続には多くの税務上の注意点がある ・アメリカにある財産で困ったら「税理士法人マインライフ」へ! 相続対策はいつから取り組み始めるかで結果に大きな違いを生みます。 早ければ早いほど、大きな効果を得ることができるのです。 これはアメリカにある財産についても同じことが言えます。 将来の相続に備えて、今できることをひとつずつ着実に行っていきましょう。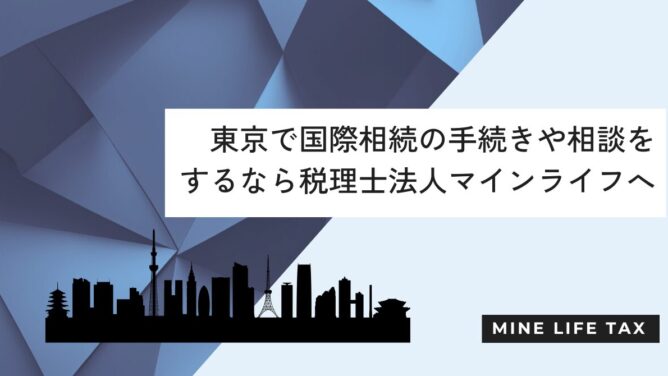
国際相続サポート
東京で国際相続の手続きや相談をするなら税理士法人マインライフへ
新宿・津田沼を拠点に、相続税申告/国際相続/相続対策に特化した「相続専門」の税理士法人です。 案件ごとに専門性の高い税理士が前面に立ち、質の高い申告と提案を提供します。 初回面談は無料です。 まずは安心してご相談ください。 税理士法人マインライフについて──相続・国際相続に強い、少数精鋭の専門チームです マインライフが選ばれる理由 ①経験の深さが、品質の差になる 相続税は税理士の経験値によって結果が大きく変わる分野。私たちは相続税申告の実務経験が100件超の税理士が必ず担当し、財産評価から申告内容のご説明、踏み込んだご提案まで直接対応します。外部任せにしない「顔が見える品質」で、ブレのない申告を実現します。 相続税申告の担当は一般的な税理士の年間1~2件に対して、私たちは税理士一人あたり年間約50件の相続税申告を担当。高度論点は所内の税理士と外部顧問で多面的に検討し、他では難しい処理にも対応できる体制を整えています。 ②国際相続までワンストップ 海外資産や海外在住相続人が絡むケースでは、各国の専門家と連携し、日本側の窓口として一気通貫でサポート。英語にも対応可能で、アメリカ、シンガポール、欧州各国など幅広いネットワークを活用します。国内・海外の名義変更や外国税額控除を含む論点まで、まとめてご相談いただけます。 ③税務調査を見据えた盤石の準備 過去の申告・税務署対応の知見をもとに、必要書類リストの整備や評価根拠の明確化など調査対応を前提にした設計で申告を仕上げます。外部顧問とも連携し、抜けや見落としのない準備でリスクを抑えます。 また、税理士法人マインライフでは「書面添付制度(税理士法第33条の2)」を標準装備します。この制度は『税理士が税務署の代わりに、納税者をしっかり調べました』という専門家の所見を述べる意見書を作成し、申告書に添付する制度です。提出することにより、そもそもの税務調査を数%に下げます。 ④わかりやすさに徹するプロの説明力 税理士専門学校の講師経験者が在籍。専門用語に頼らず、本質からかみくだいてお伝えする姿勢を徹底しています。これは「高い専門性と提案力で顧客の発展に貢献する」という基本理念にも根差しています。 金融機関での外部セミナー開催/メガバンク内部行員勉強会などでもわかりやすく専門的な内容は大変好評いただいております。 YouTube「相続税理士カドクラの恐縮チャンネル」相続に関する情報を、どこよりも分かりやすく解説します! 第1章 プランの内容 税理士法人マインライフでは、お客様の状況に応じ以下の国際相続のサポートを行います。 国際相続の状況 主なサポート 海外に財産がある ・日本の相続税申告・評価 ・海外での名義変更やプロベート要否の判断 ・金融機関・現地専門家との連携 ・翻訳・認証の段取り 相続人が海外在住 or 外国籍 ・署名証明・領事認証・アポスティーユの要否判断 ・本人確認書類の整合(氏名表記ゆれ等) ・相続登記・銀行手続の要件整理 ・納税管理人の選任・届出 被相続人が外国籍 ・課税範囲の確認(居住歴・国籍等) ・準拠法の整理 ・日本申告と各国手続の並走管理 ・必要書類の翻訳・認証手配 必要に応じて外部専門家の弁護士(海外・日本)、司法書士などと連携しワンストップで国際相続のサポートを行います。 ※プロベート=遺産の内容や相続人を裁判所の管理下で確認・整理する手続きです。 詳しくは下記の記事をご参照ください。 「プロベートの記事(後日投稿予定)」 ※アポスティーユ=ハーグ条約加盟国間で公文書を海外で使うために、文書が正規に作成されたものであることを証明するもの。 以下のご相談・サポートをしております。 事例① 被相続人が外国籍で、海外にも財産があったケース 【状況】 被相続人は外国籍で日本に居住。財産は日本と海外の両方にあります。 【サポート】 日本側:当法人で財産の評価(日本・海外)と日本の相続税申告、必要書類の整理、期限管理を行います。相続税相当の課税がある国の場合には外国税額控除により二重課税の調整。 海外側:提携の日本の弁護士と現地の弁護士で連携して、プロベート(裁判所の手続き)や名義変更・換金を進めます。相続税相当の課税がある国の場合には必要に応じて現地の専門家と連携し海外の申告を進めます。 日本の申告に必要な海外資産の評価額・基準日を早めに固めるため、海外の進行と並走します。 【結果】 海外の名義変更・換金・海外の申告と日本の申告を同時並行で期限内に無事完了。 事例② 相続人の一人が海外在住だったケース 【状況】 相続人のうち一人が海外居住。財産は日本にあります。 【サポート】 納税管理人が必要なため選任後、納税管理人届出書の提出。場合によっては当法人にてお受けします。 海外にいる相続人の署名証明(署名の本物確認)と在留証明の取得方法を案内。必要に応じて翻訳を行います。 必要書類リストを提示し、抜け漏れを防止。 時差や郵送時間を見込みつつ、申告期限(10か月)から逆算して「分割協議~申告まで」のスケジュールを提示。 アメリカでは年間10万ドルを超える財産をアメリカ以外の国から相続で受けると「Form3520」の提出が必要。現地の専門家と連携し海外の申告を進めます。 財産が海外にもあるケースでは、海外居住の相続人については過去の住所履歴などから日本での納税義務・課税される範囲を確定させます。 【結果】 期限内に協議成立し、申告・納税まで完了。 第2章 国際相続を依頼する場合の費用 税理士法人マインライフでは、以下の報酬規定により国際相続のサポートを行います。 報酬規定について【国際相続サポート】👈 遺産総額 報酬額 (税込金額) ~7,500万円 1,155,000円 ~1億円 1,443,750円 ~2億円 2,310,000円 ~3億円 3,080,000円 3億円~ 別途お見積もり ※ 国際相続サポート(上記報酬表)は、日本の相続税申告が必要となる場合で以下に該当するものを対象とします。 〇相続財産が海外に所在している 〇被相続人または相続人に海外居住者がおり、海外の相続税申告が必要 〇被相続人または相続人に外国籍の方がいる 〇相続人が日本語を話せない ※ 上記の報酬には、海外財産の相続手続きや海外の相続税申告にかかる現地の専門家の報酬は含んでおりません。 ※ 上記の報酬には、日本における遺産分割協議書の作成、書面添付制度の対応、2次相続税対策シミュレーションの作成が含まれております。 ※ 土地の数や相続人の人数による報酬の加算はございません ※ 「遺産総額」とは、相続税計算上の財産評価額の総額のことであり、 小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金の非課税、借入金等の債務、配偶者の税額軽減を控除する前の金額となります。 ※ 財産に非上場株式を含む場合、延納・物納をご希望の場合は、内容に応じて別途お見積りさせていただきます。 ※ ご依頼の時期が申告期限まで3か月を切っている場合、お急ぎ対応料金の加算をお願いすることがございます。 ※ 特殊事情により通常よりも多くの作業が必要となる場合 (例:有価証券を100銘柄以上有している場合、遺産分割案に基づく相続税シミュレーションの作成が10パターン以上に及ぶ場合など) は、別途お見積りさせていただくことがございます。 ※ 税務調査が実施される場合には日当110,000円、また修正申告が必要な場合は別途修正申告手数料(税込220,000円~)を頂戴しております。 ※ 戸籍等の資料取得代行をご依頼いただいた場合には、これにかかる手数料と実費のご負担をお願いいたします。 ※ 財産の現地調査やご訪問に伴う旅費交通費等の実費のご負担をお願いいたします。 ※ 所得税の準確定申告につきましては、別途お見積もりさせていただきます。 第3章 国際相続をご依頼いただく場合の流れ 税理士法人マインライフでは、国際相続のサポートを初回面談から相続税申告まで以下の流れで行います。 ①無料の初回面談・ヒアリング まずは相続人や被相続人の国籍、居住地、国内外の財産の種類や規模などを丁寧にヒアリングします。 特に国際相続の場合、国ごとに制度や必要書類が異なるため、最初の情報整理が非常に重要です。お客様の不安や疑問もこの段階でしっかり伺い、全体の流れを分かりやすくご説明します。 その後、ヒアリング内容に基づいて必要な対応範囲を整理し、見積りを作成、ご提示いたします。 ②相続人・財産調査 次に、相続人と国内外の財産の状況を確認します。 海外の不動産、証券口座、銀行預金などは評価方法や手続きが日本と異なるため、特殊な評価・証明書類の取得が必要です。私たち が中心となって必要な書類のリスト化や取得方法のご案内を行い、相続人が迷わず準備を進められるようサポートします。 取得した資料を基に、日本の相続税額を確定し申告書を提出します。必要に応じて正しく外国税額控除を適用し、二重課税を回避 します。相続税の外国税額控除の記事はこちら 相続税申告は高度な専門知識を要し、誤りがあると余計な税負担や追徴課税が発生することとなります。私たちは豊富な経験を活かして正確な申告を行います。また、申告後に税務署から問い合わせがあった場合も税務署とのやり取りを代理対応します。 ③海外専門家との連携 相続財産が所在する国ごとに法律や会計の専門家と連携し、必要な書類の収集や手続きを進めます。 言語や制度の壁がある部分も、私たちが窓口となることでスムーズに対応可能です。現地弁護士や会計士等と直接連絡を取りながら、期限内に必要資料を揃えられるよう調整します。 ④外国税額控除・相続税申告 整理した資料を基に、日本での相続税申告を代理し、外国税額控除を正しく適用して二重課税を回避します。 国際相続の申告は高度な専門知識を要し、誤りがあると余計な税負担や追徴課税につながりかねません。私たちは豊富な経験を活かして正確な申告を行い、必要に応じて税務署とのやり取りも代理対応します。 第4章 お悩みは無料相談へ 税理士法人マインライフでは、国際相続に関する疑問点やお悩みを解消するために、初回無料相談を実施しています。 こんなお悩みはありませんか? 「相続人が日本国外在住で手続きが複雑」「海外の不動産や有価証券の評価方法が分からない」「二重課税によって税負担が増えないか不安」「外国税額控除が正しく使えるか心配」「海外の専門家とのやり取りが難しい」など 国際相続に精通した税理士が疑問点やお悩みを伺い、不安を解消します。 以下のご相談例についてアドバイス・サポートを行っております。 相談例① 相続人が日本国外在住で手続きが複雑 課題:日本と海外のやり取りが複雑で、必要書類・手順が不明確。 相続開始から申告までのスケジュールを提示し、必要書類・翻訳などの流れを整理。 私たちが日本側の窓口となり、英語での連絡や現地専門家との調整方針を決定。 連絡経路・役割分担が一本化し、海外居住の相続人でも負担を最小化して手続きを進められます。 相談例② 海外の不動産や有価証券の評価方法が分からない 課題:評価基準・根拠資料・現地証憑の集め方が不明。 評価方針と収集すべき証憑をリストで可視化。各財産の相続税評価は私たちが行います。 評価プロセスと根拠・必要資料が明確になり、海外資産も含めて申告準備をスムーズに進めます。 相談例③ 二重課税によって税負担が増えないか不安 課題:海外でも課税がありそうで、日本と重複しないか心配。 対象国の課税有無・範囲を確認します。外国税額控除の適用可能性や適用時の留意点を説明します。 二重課税リスクへの対処方針が定まり、安心して国内外の手続きを進められます。 相談例④ 海外の専門家とのやり取りが難しい 課題:現地の弁護士・会計士などの専門家とのコミュニケーションや段取りに不安。 財産所在国の提携専門家ネットワークを提示し、私たちがハブとなってやり取りを代行。英語対応も行います。 国をまたぐ実務をワンストップで進行し、相続人の時間的・心理的負担が大幅に軽減できます。 そのほか、ヒアリング内容に基づいて必要な対応範囲を整理し、見積りを作成、ご提示いたします。 ご相談は、新宿・津田沼にオフィスを設置しておりますので、ご希望の場所にお越しください。 直接お会いすることが難しい方には、オンラインでも相談を行っております。 初回無料相談はこちらから↓ LINEで相談👈 面談予約はこちらから👈 第5章 国際相続専門の強み 国際相続に強い税理士に必ず依頼してください。 ①手続きをスムーズに進められる 国際相続専門の税理士に依頼することで複雑な国際相続も円滑に進められるという点が最大のメリットです。 相続税の申告に必要な書類を的確にリストアップし、役所や金融機関、さらには様々な専門家と連携して手続きを任せられるため、依頼者自身が一から調べて動く手間を大幅に省けます。 経験豊富な税理士に任せれば安心して手続きを進めることができます。 ②税金を払いすぎるリスクを防げる 国際相続では、二重課税や不要な税負担のリスクが国内相続に比べてはるかに大きいのが現実です。 たとえば、日本の相続税と米国の遺産税の両方が課税されるケースもあります。 しかし、国際相続専門の税理士であれば、租税条約や外国税額控除といった制度を正確に適用して計算し、税金を最小限に抑えることが可能です。 ③税務調査時にも安心して税理士に任せることができる 国際相続専門の税理士であれば、税務調査が入っても安心して対応を任せられます。 近年、国際的な資産移動や海外口座の情報開示が進んだことにより、税務署が国際相続案件に注目するケースは増えています。 国際相続では、海外財産の申告漏れや評価の誤り、二重課税調整の計算ミスなどが指摘されやすく、一般的な相続案件に比べて税務調査の対象となる可能性が高いのが実情です。 しかし、国際相続専門の税理士であれば、事前の申告段階でリスクを洗い出し、調査で問われやすいポイントに備えた対応を準備が可能です。 また、実際に税務調査が行われた場合でも、税理士が前面に立って説明や資料提出を行うため、依頼者本人が直接やり取りをして不安を感じる必要はありません。 「調査が入ったらどうしよう」という不安を和らげ、安心して相続を進められることを実現します。 第6章 税理士の紹介 国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑で、専門家の存在が成功の分かれ道となります。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼と東京近郊を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 法人名称 税理士法人マインライフ 税理士法人番号 第5095号 代表社員 統括代表社員 門倉 誉士希 (税理士登録番号129249) 代表社員 伊藤 千尋 (税理士登録番号136705) 代表社員 久保 佑介 (税理士登録番号140334) 代表社員 川崎 朝輝 (税理士登録番号145456 ) 所属団体 東京税理士会 四谷支部(東京事務所) 千葉税理士会 千葉西支部(千葉事務所) 所在地 東京事務所(本社) 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH 6階 TEL:03-6856-4314 千葉事務所 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼7-10-8 最新の税理士紹介のページはこちら👈 第7章 まとめ 本記事では、「東京で国際相続の手続きや相談をする」場合において弊社の以下の内容を説明させていただきました。 第1章 東京で国際相続をする場合の費用 第2章 プランの内容 第3章 国際相続をご依頼いただく場合の流れ 第4章 お悩みは無料相談へ 第5章 国際相続専門の強み 第6章 税理士の紹介 国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑です。 「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」―― 少しでも不安がある場合には、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。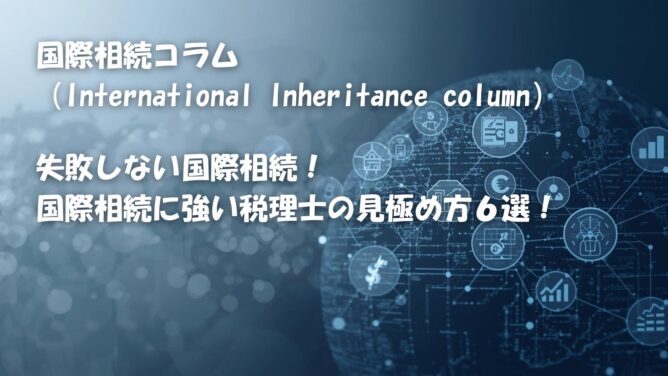
国際相続サポート
失敗しない国際相続!国際相続に強い税理士の見極め方6選!
ご両親の相続手続きについて調べ始めたとき、当初は日本国内で完結する手続きだと思っていたのではないでしょうか。 ところが実際に財産や相続人を確認すると、「相続人の一人が海外に住んでいる」「相続財産の一部が海外にある」といった状況が判明し、突然「国際相続」という言葉に直面し戸惑っているかと思います。 結論からお伝えすると、相続に海外が絡む場合は国際相続の経験やネットワークを持つ税理士に早めに相談することが必須です。 国際相続は、国内の相続よりも格段に複雑で、法律・税制・言語が絡み合うため、専門家のサポートなしに完結させることは不可能です。 また、専門家の中でも国際相続の経験がない税理士に頼んでしまうと「手続きが進まない」「税金を払いすぎてしまう」といった深刻なトラブルに発展する可能性があります。 本記事では、実際に依頼すべき「国際相続に強い税理士」の選び方や相談するメリットを分かりやすく解説します。 海外に関わる相続で悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。 第1章 国際相続の相続手続き 国際相続が必要な場合は、なぜ非常に複雑な手続きとなるのか、国際相続の手続きが必要な場合を簡潔にお伝えしたうえで、国際相続だからこその特徴をまとめました。 1-1. 国際相続の手続きが必要な場合とは 結論から言えば、「海外に被相続人の財産がある」、「相続人が海外に住んでいる」といった場合は国際相続の手続きが必要です。 例えば、被相続人が日本に住みながら海外に不動産や銀行口座を持っていた場合、または相続人が海外在住の場合、通常の日本の相続の手続きだけでは処理できません。 国や地域ごとに相続制度や課税ルールが異なるため、国際相続の枠組みで対応しなければならないのです。 1-2. 国際相続の手続きは複雑 国際相続の手続きは、日本での手続きと海外での手続きの両方が必要になるため複雑です。 具体的には、海外に財産がある場合には日本での遺産分割協議や相続税申告と並行して、現地でのプロベート(裁判所手続き)や相続税の申告が必要になるケースがあります。 現地での申告やプロベートはその国の言語・制度・税制が絡み合うため、現地の弁護士とのやり取りが必須になります。 その結果、通常の相続より時間も労力もかかることになってしまいます。 1-3. 国際相続の手続きは早期の対応がカギ 国際相続の成功は初動の早さで決まります。 国際相続であっても、日本の相続税申告期限は相続開始から10か月以内と定められています。 ところが、海外の金融機関や裁判所から必要な証明書や残高証明を取り寄せるには、数か月以上を要することが多いです。 それに加えて国際相続は翻訳や認証手続きも加わるため、国内手続きに比べて格段に時間がかかります。 また、申告期限間近で税理士に依頼するなど手続きに動くと以下のようなデメリットがあります。 ・税理士に依頼する場合、申告期限間近では通常のケースよりも追加で報酬が必要になる。 ・概算の内容で申告をして後々で修正申告をすることになり、延滞税や加算税(ペナルティ)がかかる。 そのため、相続が始まった段階から迅速に動き、専門家と連携しながら準備を進めることが重要です。 1-4. 国際相続の専門家に任せた方が良い 間違いなく国際相続は国際相続の経験がある専門家に依頼すべきです。 制度の違いや二重課税リスクを正しく処理できるのは、経験豊富な国際相続に強い税理士や弁護士のチームだけです。 実際に私が係わってきた中でも、以下のようなケースが多いです。 ・当初普段から付き合いのある税理士に依頼していたが、手続きが全く進まず途中から弊社に依頼していただいた。 ・相続を専門とする税理士に依頼しようと相談にいったが国際相続は対応できないと言われた。 日本の相続税の申告件数を税理士の登録者数で割ると一人当たり年間1~2件になります。 しかし、実際には弊社のように年間100件以上相続税申告を行っている税理士法人もあるため、税理士の中には相続税申告は1年間に1件も行わない税理士も多くいるので特殊な業務とされているのです。 国際相続はその中でも100件に2~3件程度になると思います。 税理士と普段接点がない方だと、どの税理士も手続きできるだろうと考えがちですが、実際に国際相続を円滑に進めることができる税理士は少ないということがお分かりになるかと思います。 したがって、国際相続の経験のある専門家に相談することが、最も効率的で安全な方法です。 第2章 国際相続に強い税理士の選び方 では、国際相続に強い税理士を選ぶときには、どんなところに注意して判断すれば良いでしょうか。 大事な6つの視点を踏まえ、自分に合った税理士を探してみてください。 2-1. 海外の専門家とネットワークがある 国際相続では海外の士業と連携できるネットワークをもった税理士が必要です。 理想論では ・日本の税務申告だけでなく、海外現地でのプロベート手続きや税務申告まで全ての知識がある。 ・日本だけでなく海外においても全ての手続きを行うことができる そんな専門家が理想です。 ただし、現実にすべてを一人又は一つの事務所で手続きを行うことは不可能です。 日本でも登記業務は司法書士の先生にお願いするように、海外の手続きは海外の専門家との協業が必須になります。 この現地とのネットワークがあるということが国際相続に強い税理士の必須条件になります。 2-2. 国際相続案件の取り扱い実績が豊富 国際相続では、通常の相続税申告はもちろん特に国際相続の経験豊富な税理士に依頼することをおすすめします。 国際相続は前述したように手続きが複雑なため時間がかかるだけでなく、日本ではない海外特有の制度に基づいた財産をどのように相続税申告に織り込むか検討するなど、非常に高度な税務判断が必要になります。 それだけ国際相続は専門性が高く、机上の知識だけでは乗り越えられないケースも多いため、経験の多さは信頼性に直結します。 【コラム】 ~ジョイント口座~ 日本にはない制度でアメリカにはジョイント口座というものがあります。 ジョイント口座とは共有で一つの銀行口座を保有することができる口座です。 一般的には夫婦で口座を作って共同で管理・利用する目的で作られます。 この夫婦で作ったジョイント口座は、夫婦の片方が亡くなった場合には、自動的に残りの名義人に口座資産が承継される設計になっていることが多いです。 ジョイント口座は日本の金融機関では認められていない制度ですが、日本の相続税申告では『被相続人が実際に出資した割合』を相続財産に計上する必要があります。 したがって、被相続人が全額出資していた場合には残高の全額を計上しなければなりません。 しかし、実務経験の少ない税理士の中には、名義を理由に誤って半分しか計上しないミスもよく見ます。 2-3. 日本の税制だけでなく海外の税制度や租税条約に詳しい 国際相続では日本の税制だけでなく海外の制度や租税条約の理解が不可欠です。 税金そのものは条約等で課税が回避されていても、海外での届出や申告の義務が残ることがあるからです。 具体例として、日本人が米国に財産を持つ場合、日米租税条約により相続税が実際に二重に課されることは少ないです。 ただし、米国では課税ゼロでもIRSへの書類提出(Form 706-NAやForm 8833など)が必要になります。 この申告を怠るとペナルティを受けるリスクがあります。 このように、国際相続では海外税制や条約に詳しい専門家の助言を受けることで、余計なリスクを避けることができます。 2-4. 料金が明確である 税理士を選ぶ際には「料金が明確である」ということも重要です。 しかし、実際に弊社に相談に来られたお客様の中にも過去に他の税理士が行った相続税申告の手続きにおいてこんな不安を口にされることが多々あります。 「見積もりより高い金額を請求された」 「追加作業ごとに費用が積み上がっていった」 「総額が最後まで分からなかった」 相続税申告は通常一生で2回程度経験するかしないかの大切な手続きです。 料金が不透明なままでは、安心して任せられません。 特に国際相続は期間が長く費用がかさみがちです。 報酬体系が透明な税理士を選ぶことが、安心につながります。 【税理士法人マインライフでは初回面談は無料かつ、明確な料金表を提示しています。】 遺産総額 報酬額(税込金額) ~7,500万円 1,155,000円 ~1億円 1,443,750円 ~2億円 2,310,000円 ~3億円 3,080,000円 3億円~ 別途お見積り ※ 国際相続サポート(上記報酬表)は、日本の相続税申告が必要となる場合で以下に該当するものを対象とします。 〇相続財産が海外に所在している 〇被相続人または相続人に海外居住者がおり、海外の相続税申告が必要 〇被相続人または相続人に外国籍の方がいる 〇相続人が日本語を話せない ※ 上記の報酬には、海外財産の相続手続きや海外の相続税申告にかかる現地の専門家の報酬は含んでおりません。 ※ 上記の報酬には、日本における遺産分割協議書の作成、書面添付制度の対応、2次相続税対策シミュレーションの作成が含まれております。 ※ 土地の数や相続人の人数による報酬の加算はございません ※ 「遺産総額」とは、相続税計算上の財産評価額の総額のことであり、 小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金の非課税、借入金等の債務、配偶者の税額軽減を控除する前の金額となります。 ※ 財産に非上場株式を含む場合、延納・物納をご希望の場合は、内容に応じて別途お見積りさせていただきます。 ※ ご依頼の時期が申告期限まで3か月を切っている場合、お急ぎ対応料金の加算をお願いすることがございます。 ※ 特殊事情により通常よりも多くの作業が必要となる場合 (例:有価証券を100銘柄以上有している場合、遺産分割案に基づく相続税シミュレーションの作成が10パターン以上に及ぶ場合など) は、別途お見積りさせていただくことがございます。 ※ 税務調査が実施される場合には日当110,000円、また修正申告が必要な場合は別途修正申告手数料(税込220,000円~)を頂戴しております。 ※ 戸籍等の資料取得代行をご依頼いただいた場合には、これにかかる手数料と実費のご負担をお願いいたします。 ※ 財産の現地調査やご訪問に伴う旅費交通費等の実費のご負担をお願いいたします。 ※ 所得税の準確定申告につきましては、別途お見積もりさせていただきます。 2-5. レスポンスが早い 国際相続においては「時間との戦い」が避けられません。 日本での相続税の申告期限(10か月)は通常の相続でも国際相続でも同じですが、海外財産や海外在住相続人が関わる場合、通常以上に調整や書類取得に時間を要します。 例えば、海外の財産のプロベート手続きには少なくとも数か月かかりますし、相続人が海外に住んでいる場合に必要な署名(サイン)証明の取得や在留証明の取得にも日数がかかります。 つまり、行動が遅いと期限内に手続きを終えるのが困難になりかねないのです。 国際相続の経験が豊富な税理士は、どの手続きに時間がかかるかを把握しており、先手を打って準備を進めてくれるため安心です。 逆に動きが遅い税理士に任せてしまうと、申告期限に間に合わず加算税や延滞税といったペナルティが発生するリスクすらあります。 2-6. 自分との相性 最後に意外と見落とされがちですが「自分との相性」こそが長期戦になりやすい国際相続では「成功のカギ」となります。 国際相続の案件は、国内完結の相続よりも解決までの期間が長引きがちです。 1年を超えることも珍しくなく、依頼者と税理士の間で頻繁にやり取りを重ねる必要があります。 もしコミュニケーションがスムーズに取れなかったり、人間的な信頼関係を築けなかったりすると、ストレスが大きくなり、かえって手続き全体に悪影響を与えかねません。 実際に相談する際には、初回面談での説明の分かりやすさやレスポンスの早さ、質問に真摯に答えてくれるかどうかなどを確認してみるとよいでしょう。 「専門知識があるかどうか」だけでなく、「安心して最後まで任せられる人物かどうか」を見極めることが、国際相続における税理士選びの最重要ポイントのひとつです。 第3章 国際相続に強い税理士に相談するメリット 国際相続に強い税理士に依頼することは、さまざまなメリットがあります。 ここではその中でも代表的なもの3点を挙げています。 3-1. 手続きをスムーズに進められる 結論として、専門家に依頼することで複雑な国際相続も円滑に進められるという点が最大のメリットです。 相続税の申告に必要な書類を的確にリストアップし、役所や金融機関、さらには様々な専門家と連携して手続きを任せられるため、依頼者自身が一から調べて動く手間を大幅に省けます。 経験豊富な税理士に任せれば安心して手続きを進めることができます。 3-2. 税金を払いすぎるリスクを防げる 国際相続では、二重課税や不要な税負担のリスクが国内相続に比べてはるかに大きいのが現実です。 たとえば、日本の相続税と米国の遺産税の両方が課税されるケースもあります。 しかし、国際相続に精通した税理士であれば、租税条約や外国税額控除といった制度を正確に適用して、正確に計算し、税金を最小限に抑えることが可能です。 これは依頼者が独力で調べるのは極めて困難な領域です。 3-3. 税務調査時にも安心して税理士に任せることができる 国際相続に強い税理士がいれば、税務調査が入っても安心して対応を任せられます。 近年、国際的な資産移動や海外口座の情報開示が進んだことにより、税務署が国際相続案件に注目するケースは増えています。 国際相続では、海外財産の申告漏れや評価の誤り、二重課税調整の計算ミスなどが指摘されやすく、一般的な相続案件に比べて税務調査の対象となる可能性が高いのが実情です。 しかし、国際相続に精通した税理士であれば、事前の申告段階でリスクを洗い出し、調査で問われやすいポイントに備えた対応を準備してくれます。 また、実際に税務調査が行われた場合でも、税理士が前面に立って説明や資料提出を行うため、依頼者本人が直接やり取りをして不安を感じる必要はありません。 「調査が入ったらどうしよう」という不安を和らげ、安心して相続を進められることこそ、専門家に依頼するメリットのひとつです。 第4章 国際相続で起こりやすいトラブルと注意点 私が今まで国際相続の対応をしてきた中で、国際相続ならではのトラブルや注意点が数多くありました。 間違いなく言えるのは、国際相続は通常の相続と比べてトラブルや注意点が多いということです。 どういったことが問題になりうるのかをわかった上で対応してくれる税理士に依頼することの重要性を理解してください。 4-1. 海外にいる相続人と連絡が取れない 海外に住んでいる相続人と連絡がつかないというのが相続手続きが進まない最大の要因の一つです。 住所不明や連絡不能のケースでは、日本の家庭裁判所で不在者財産管理人の選任手続きが必要になることもあります。 これには時間も費用もかかるため、早めに把握して対策を講じることが大切です。 4-2. 国ごとのルールが違うため思わぬ税金が発生 国際相続の大きな落とし穴は、各国の税制や相続制度が異なることです。 例えば、日本では相続税課税ですが、米国では遺産税課税という違いがあり、同じ財産に二重に課税されることもあります。 こうしたリスクを未然に防ぐためにも、租税条約や国ごとのルールを理解している税理士に依頼する必要があります。 4-3. 手続きを進めるのに時間と費用がかかる 国際相続は、翻訳や公証、裁判所手続きなどが必須となる場合が多く、国内相続の数倍の時間とコストがかかるのが実情です。 依頼前にあらかじめスケジュールや費用の見通しを確認しておくことが、予期せぬトラブルを防ぐポイントです。 第5章 国際相続の手続きの流れと専門家の関わり一覧 国際相続は、国内相続と異なり「国をまたいだ手続き」が必要になる点が大きな特徴です。 財産や相続人の居住地によって、手続きの進め方や関わる専門家が大きく変わってきます。 まずは全体像をつかむために、以下のようなケース分けが考えられます。 ケース 相続人の住所 (ケース4のみ被相続人の国籍) 財産のある場所 主な課題 関与する専門家 1 海外在住者あり 日本国内のみ 書類の署名取得や公証・翻訳に時間がかかる 日本:税理士・司法書士・弁護士 2 日本国内のみ 海外財産あり 海外財産の評価・プロベート※による長期化 日本:税理士、弁護士 海外:現地弁護士・現地会計士等 3 海外在住者あり 海外財産あり 時差・言語・制度差による調整負担、二重課税リスク 日本:税理士、弁護士 海外:現地弁護士・現地会計士等 4 被相続人が外国人 海外財産あり 準拠する法の確認が必須、二重課税リスク 日本:税理士・弁護士 海外:被相続人本国の専門家(弁護士等) ※プロベート:裁判所による遺産承認手続き 5-1. 財産は国内にあるが、相続人のいずれかが海外にいる場合 このケースでは、財産は日本国内にしかないため、基本的な相続手続きは日本の法律に基づきます。 ただし、相続人が海外に住んでいる場合、署名や同意書類を取り付けるのに時間がかかるのが特徴です。 具体的には、在外公館(大使館・領事館)で署名証明を受ける必要があります。 この場合書類を国際郵便でやり取りするため、数週間〜数か月かかることもあります。 このため、早めに専門家に依頼し、署名書類のフォーマットを整えてから相続人へ送付するのがスムーズです。 5-2. 国外に財産があるが、相続人は全員国内にいる場合 相続人が全員日本に住んでいても、財産が海外にある場合は現地での手続きが必要となります。 たとえば、米国に不動産や証券口座がある場合はプロベート(遺産承認手続き)が必要になるケースが多く、裁判所を通さないと名義変更や解約ができません。 プロベートには数か月〜数年かかることもあり、その間に日本の相続税申告期限(10か月)は到来します。 また、不動産であれば現地の鑑定評価書を入手して翻訳しておくといった準備が欠かせません。 このため、日本の税理士と並行して現地の弁護士・会計士を早めに手配する必要があります。 国際相続の経験が豊富な専門家であれば、現地とのネットワークを有しており円滑に相続手続きを進めることができます。 5-3. 財産も相続人も海外にいる場合 最も複雑で時間を要するのがこのケースです。 その理由としては下記の2点が大きな理由です。 ・財産の評価は、海外の銀行や不動産業者から資料を取り寄せる必要がある。 ・相続人同士のやり取りは時差・言語の壁があり間に専門家がたち調整をする必要がある また、日本と海外の双方で相続税がかかる可能性(二重課税リスク)があります。 このような場合は、日系と現地の専門家が連携してサポートする体制が必須です。特に、税理士が租税条約や外国税額控除を駆使して調整しないと、余計な税負担が生じることがあります。 5-4. 被相続人が外国人の場合 被相続人が外国籍の場合は、相続に適用される法律が本国法か日本法かをまず確認する必要があります。 民法では「被相続人の本国法が相続に適用される」とされているため、その国の相続制度を無視することはできません。 ただし、財産が日本にある場合は日本法が優先されることもあるため、準拠法の判断が非常に重要になります。 また、戸籍が存在しないため、出生証明や婚姻証明などを本国から取り寄せる作業が必要になります。 相続税については、被相続人や相続人が外国籍であっても、日本に住所や財産があれば課税対象になります。 このケースも日本の税理士・弁護士に加えて、被相続人の国の弁護士や会計士のサポートが必須になりますので早期に専門家に依頼することを強くおすすめします。 第6章 国際相続は「税理士法人マインライフ」へ 国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑で、専門家の存在が成功の分かれ道となります。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」―― そのようなときは、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 最初の一歩を踏み出すことが、複雑な国際相続を解決へ導く最大のカギとなります。 第7章 まとめ いかがだったでしょうか。 国際相続は、制度の違い・言語の壁・申告期限の厳しさから、放置すると大きなトラブルに発展する可能性があるとお分かりいただけたかと思います。 税理士には様々な特性や専門がありますが、国際相続を安心して任せられる税理士の特徴は以下の5つ6つです。 ・海外の専門家とネットワークがある ・国際相続案件の取り扱い実績が豊富 ・日本の税制だけでなく海外の税制度や租税条約に詳しい ・料金が明確である ・レスポンスが早い ・自分との相性 「海外財産がある」「相続人が海外在住」と分かった時点で、すでに国際相続の枠組みに入っている可能性が高いため、できるだけ早く専門家に相談することが不可欠です。 国際相続に強い税理士に依頼することで、スムーズな手続き、過大な税負担の回避、そして相続人同士の円満な関係維持が実現できます。早めの一歩が、安心の相続につながります。
国際相続サポート
海外に財産や相続人がいる場合の相続手続きと税金を税理士が徹底解説します
「海外に財産があるけれど、その相続手続きは問題ないだろうか」 「子どもが海外に住んでいるけれど、ちゃんと財産を相続できるだろうか」 そんな悩みを持つ方が増えています。 グローバル化が進み、国をまたいだ相続、いわゆる「国際相続」が増えている一方、その手続き、税金の取り扱いはとても複雑です。 本記事では、国際相続の手続きと税金の概要について整理し、何に注意すべきか、ということを分かりやすく説明します。 将来の国際相続に備え、今自分がすべきことを把握し実践していきましょう。 第1章 国際相続とは? まず、「国際相続」とはどんな相続のことを言うのか、その定義と通常の日本国内の相続との違いを確認しましょう。 1-1 国際相続の定義と特徴 まず、国際相続とは、一言で言うと「国をまたぐ相続」です。 具体的には、相続の当事者である被相続人(亡くなった人)や相続人(遺産を相続する人)、または相続財産が複数の国にまたがっている場合を言います。 例えば、以下のようなケースの相続です。 ・被相続人(亡くなった人)や相続人(遺産を相続する人)に海外に住んでいる人がいる ・被相続人(亡くなった人)が海外に財産を持っている ・被相続人(亡くなった人)や相続人(財産を相続する人)に外国籍の人(外国人)がいる 【国際相続のイメージ】 これらのケースでは、日本国内の相続と比べて、「どの国の法律を適用するか」「どの国で税金が発生するか」という判断が必要となります。 つまり、国際相続は「法律」と「税金」の両面で複数の国のルールが絡み合うのが最大の特徴です。 1-2 日本国内の相続との違い 日本国内だけで完結する相続の場合、適用されるのは原則として日本の法律である民法と相続税法です。 財産の把握から遺産分割協議、不動産の相続登記や口座解約、そして相続税申告まで、その手続きは国際相続に比べるとシンプルです。そして、これに対応できる日本国内の専門家(弁護士や税理士等)も数多く存在します。 一方、国際相続では次のような違いが生じます。 日本国内の相続と国際相続の比較 国際相続では海外の専門家との連携が必要となるため、日本の窓口となる日本の専門家にはその対応力が求められます。 1-3 国際相続のポイント 国際相続における相続手続きの一般的なポイントをざっくりとまとめると以下の通りとなります。 ・相続人が海外に住んでいる場合は、サイン証明書や在留証明書が必要となる。 ・財産が海外にある場合は、現地の法律に従った相続手続きが必要(プロベート手続きは大変)。 ・亡くなった人、または、相続人が外国籍の場合には、戸籍の代わりとなる相続関係を証明する書類(出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書、宣誓供述書など)が必要。 ・日本と海外両方の相続税(遺産税)が発生する可能性がある。その場合、二重課税を防止するための外国税額控除の検討が必須。 以下にさらに具体的に国際相続のポイントを見ていきましょう。 第2章 国際相続となる典型的なケースとその手続きのポイント 次に国際相続となるよくあるケースとその具体的な手続きのポイントについて紹介します。 2-1 日本国籍の相続人(財産を相続する人)が海外に住んでいる もっともよくあるのが、日本に住んでいる日本国籍の方が亡くなり、その相続人(日本国籍)の一人が海外に住んでいるケースです。この場合の相続手続きには以下のような留意点があります。 なお、亡くなった方の遺産は日本に所在しているものだけ、という前提としています。 (1)手続きのポイント 相続人が海外に住んでいる場合でも、遺産分割協議や遺産の名義変更手続きの基本的な流れは通常の日本国内の相続の場合と同じです。手続き自体は日本の法律に基づき日本国内で進めるためです。 ただし、通常の日本国内の相続の場合に加えて、以下の追加のステップが必要となります。 海外に住む相続人がその居住地の在外公館(大使館、総領事館)へ出向き、以下の書類を取得する。 ・サイン証明書(印鑑証明書の代わり) ・在留証明書(住民票の代わり) (2)手続きに必要な書類 手続きにあたっては、在外公館(大使館、総領事館)で「サイン証明書」と「在留証明書」を取得する必要があります。 通常、相続による名義変更手続きなどを行う場合には手続き先の法務局や金融機関から「印鑑証明書」や「住民票」の提出を求められます。しかし、海外に住んでいる方はこれらの書類が発行されないため、これに代わる書類として「サイン証明書」と「在留証明書」を提出することとなります。 通常、日本にある財産の相続手続きにあたっては以下の書類が必要となります。 ・相続を証明する書類(戸籍) ・住所を証明する書類(住民票等) ・遺産分割協議書と印鑑証明書(遺言が無い場合) (3)手続きの注意点 ①海外に住んでいる相続人がいる場合は遺産分割協議に時間を要する 相続人が海外に住んでいる場合は以下のような理由で遺産分割協議の成立に時間を要することが多いため、注意が必要です。 ・相続人が海外に住んでいる場合、時差があるため、話し合いのタイミングが限られる ・海外に住む相続人は遺産分割協議書に自筆の署名をする必要があり、国際郵便等による書面のやり取りに日数を要する ・遺産分割協議書に添付するサイン証明書を取得するための在外公館の予約が数週間先まで取れないことがある ○遺産分割協議が遅れるリスク その1 亡くなった方の遺産は、原則的に相続人全員の同意に基づく遺産分割協議が成立しなければ財産の換金や相続人への名義変更をすることができません。 例えば日本の相続税がかかる場合、その申告・納税期限は財産を持っていた方が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっており、それまでに財産の換金や相続人への名義変更が完了していなければ納税資金が不足してしまう可能性があります。 ○遺産分割協議が遅れるリスク その2 日本の相続税には遺産分割協議が整っていないと受けられない特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)があり、期限までに遺産分割協議が整っていない場合には一度特例を使わない前提での申告・納税が必要となり、一時的な税負担が大きくなってしまいます。(遺産分割協議が整った後、「更正の請求」という手続きを行うことで税金の還付を受けることが可能です。) 以上のようなリスクがあることから、相続人に海外に住んでいる方がいる場合は早くから遺産分割協議を進めることが重要です。 ②国外転出時課税に注意 日本に住んでいて、1億円以上の有価証券を保有する人が亡くなった場合で、 ・海外に住んでいる相続人が当該有価証券を相続するとき もしくは、 ・被相続人が亡くなった日から4か月(準確定申告の申告期限)以内に遺産が未分割であるとき など に該当する場合は、準確定申告(被相続人の亡くなった年分の所得税の確定申告)において当該有価証券を譲渡したものとみなして所得税の計算を行い納税しなければなりません。 相続人が海外に住んでいるケースでは、この制度に当てはまってしまう方も少なくないと思われますので注意が必要です。 (4)日本の相続税と海外の相続税 日本の相続税は日本に住んでいる方が亡くなった場合は海外にある財産を含むその全ての財産が対象となります。 相続人が海外に住んでいるからといって、日本の相続税がかからなくなる、ということはありません。 また、相続人の住んでいる国(州)の相続税が発生する可能性もあるため注意が必要です。 2-2 日本に住んでいた被相続人(亡くなった人)が海外に財産を持っている 次によくあるのが、日本に住んでいた日本国籍の被相続人(亡くなった人)が海外に不動産や金融資産といった財産を持っているケースです。この場合の相続手続きには以下のような留意点があります。 なお、亡くなった方の相続人は日本国籍で日本に住んでいる方だけ、という前提としています。 (1)手続きのポイント 海外にある財産については、その所在地の法律に従って相続手続きを行わなければなりません。 例えば、アメリカ(主にハワイやカリフォルニア)に別荘を所有していたり、海外の証券口座や預金口座を持っていたりするケースが典型です。 この場合、財産の所在地の法律に従って財産がある国(州)で別途相続の手続きを行わなければならないことが通常です。 例えば、アメリカにある財産を相続するにあたっては、原則としてアメリカでのプロベート手続き(遺産を裁判所の監督のもとで整理・分配する手続き)が必要となり、現地の弁護士や裁判所の関与が無ければ解約や名義変更といった相続手続きができないこととなります。このプロベート手続きには相当の時間(通常半年~数年)と専門家に対する費用を要することになります。 【「プロベート手続き」についてはこちらの記事をご参照ください。】 (2)手続きに必要な書類 海外にある財産を相続するにあたって必要となる書類は財産の所在地の法律により異なりますが、主に以下のような書類は必要となることが通常です。 【必要書類の例】 ・被相続人の死亡診断書(英訳し公証したもの) ・相続人を証明する戸籍(英訳し公証したもの) ・遺言書(作成している場合) 実際には現地の専門家と連携して必要となる書類を確認していくこととなります。 (3)手続きの注意点 海外の財産を相続するにあたってプロベート手続き等が必要となる場合、その手続きには数年を要する場合もあります。 一方、日本の相続税の申告・納税期限は原則的に財産を持っていた方が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっており、この期限までに海外の財産(評価額)の確定、相続による納税資金の確保ができない可能性があります。 そして、この期限に申告・納税が遅れると「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティの税金が発生し、最悪の場合、財産が差し押さえられることとなります。 これを防ぐために、以下のような対応が必要となる場合があります。 ・申告期限までに一旦仮の内容で相続税申告書を提出し、財産が確定次第、修正の申告(更正の請求)を行う。(無申告加算税が発生することを防ぐ) ・納税できる分の納税をした上で不足分の税金については「換価の猶予」の申請を行う。(財産が差し押さえられたり、延滞税の利率が上昇することを防ぐ) どのような対応を行うかについては、その相続ごとに個別の判断が求められます。 税金の申告には期限があり、これを過ぎると取り返しがつかない損失が発生することも多々あります。 海外に財産がある場合の相続税申告については国際相続に詳しい税理士のアドバイスを受けることが肝要です。 (4)日本の相続税と海外の相続税 日本の相続税は日本に住んでいる方が亡くなった場合は海外にある財産を含むその全ての財産が対象となります。 また、財産の所在している国(州)の相続税が発生する可能性もあり、この場合、日本と海外の両方で課税される「二重課税のリスク」があることとなります。 この二重課税を防ぐため、租税条約や外国税額控除の適用の確認が欠かせません。 2-3 被相続人が外国籍(日本在住)、または、外国籍(日本在住)の相続人がいる 次によくあるのが、被相続人(亡くなった人)が外国籍で日本に住んでいる場合、または、相続人が外国籍で日本に住んでいるケースです。この場合の相続手続きには以下のような留意点があります。 なお、説明に当たり、 ・被相続人(亡くなった人)が外国籍で日本に住んでいる場合→相続人は日本国籍で日本に住んでいる前提 ・相続人が外国籍で日本に住んでいる場合→被相続人(亡くなった人)は日本国籍で日本に住んでいる前提 とします。 (1)手続きのポイント(準拠法) ①被相続人(亡くなった人)が外国籍で日本に住んでいる場合の手続きのポイント(準拠法) 被相続人(亡くなった人)が外国籍の場合、日本の法律に従うと、原則的には被相続人(亡くなった人)の本国法(国籍を持っている国の法律)に基づいて相続の内容(法定相続人や相続分など)が決まることとなります。 ただし、例えばその本国の法律が、「不動産は所在地の法律に従うこと」と定めている場合は不動産が所在する国の法律に従うこととなります。この場合結果的に、日本に所在する不動産は日本の法律に基づいて相続の内容(法定相続人や相続分など)が決まることとなります。 被相続人の本国法によって取り扱いが異なることとなり、また、本国法によっては被相続人の財産の種類、財産の所在地、生活の本拠地がどこであるかで最終的に従うべき法律が異なることとなります。 海外の財産について相続による名義変更手続きを行う場合、準拠法が日本法となる場合においても、実際の名義変更手続きが日本の法律に従って進められるかというとそのようなことはほとんどなく、財産所在地の法律に従わなければ名義変更手続きができないことが通常です。 例えば、アメリカでは原則としてプロベート手続き(遺産を裁判所の監督のもとで整理・分配する手続き)が必要となり、プロベート手続きには相当の時間(通常半年~数年)と費用を要することになります。 【「プロベート手続き」についてはこちらの記事をご参照ください。】 ②相続人が外国籍で日本に住んでいる場合の手続きのポイント(準拠法) 被相続人が日本国籍の場合、被相続人の本国法である日本の法律に基づいて相続の内容(法定相続人や相続分など)が決まることになります。 この場合、相続人の国籍は一切関係ないため、相続人が外国籍であったとしても日本国籍の相続人である場合と同じ整理となります。 海外の財産について相続による名義変更手続きを行う場合、準拠法が日本法となる場合においても、実際の手続きは財産所在地の法律に従わなければ進められないことが通常です。 実際の相続手続きにあたっては国際相続に精通する現地の専門家に確認を行う必要があります。 (2)手続きに必要な書類 ①被相続人(亡くなった人)が外国籍で日本に住んでいる場合の必要書類 ・日本国内の財産の相続手続きに必要な書類 被相続人が外国籍の場合、日本国内の財産について日本の法律に従って相続手続きを進められる場合であっても、実際の手続きにあたっては不動産の相続登記や金融機関に提出すべき必要書類が揃わないという問題が生じます。外国籍の人(外国人)には戸籍が無いためです。 したがって、戸籍に代わる以下のような書類を集める必要があります。 【戸籍に代わる書類】 ・外国籍である被相続人及びその両親、きょうだい等の出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書 等 ・宣誓供述書(相続人が被相続人との関係及び被相続人の法定相続人を確認する内容のもの) ・外国人登録原票、日本における出生届、婚姻届 等(日本に居住する被相続人の場合) なお、これらの書類は外国語で作成されるため、手続きに使用するにあたっては日本語訳を添付する必要があります。 【再掲】通常、日本にある財産の相続手続きにあたっては以下の書類が必要となります。 ・相続を証明する書類(戸籍) ・住所を証明する書類(住民票等) ・遺産分割協議書と印鑑証明書(遺言が無い場合) ・海外の財産の相続手続きに必要な書類 海外にある財産を相続するにあたって必要となる書類は財産の所在地の法律により異なりますが、主に以下のような書類は必要となることが通常です。 【必要書類の例】 ・被相続人の死亡診断書(英訳し公証したもの) ・相続人を証明する戸籍又は宣誓供述書(英訳し公証したもの) ・遺言書(作成している場合) 実際には現地の専門家と連携して必要となる書類を確認していくこととなります。 ②相続人が外国籍で日本に住んでいる場合の必要書類 ・日本国内の財産の相続手続きに必要な書類 被相続人が日本国籍である場合、その準拠法は日本の法律となり、日本国内の財産の相続手続きを行う場合には一般的な日本の相続手続きと大きく変わることはありません。 しかし、その相続人が外国籍である場合、戸籍が無いためこれに代わって以下のような書類を集める必要があります。 ・外国籍の相続人の出生証明書、婚姻証明書 等 ・宣誓供述書(相続人が被相続人との関係及び被相続人の法定相続人を確認する内容のもの) ・外国人登録原票、日本における出生届、婚姻届 等(日本に居住する相続人の場合) なお、これらの書類は外国語で作成されるため、手続きに使用するにあたっては日本語訳を添付する必要があります。 ・海外の財産の相続手続きに必要な書類 相続人が外国籍であっても、海外の財産の相続手続きに必要な書類は、上記「被相続人(亡くなった人)が外国籍で日本に住んでいる場合の必要書類」と同様となります。 (3)手続きの注意点 被相続人(亡くなった人)が外国籍の場合、または、相続人が外国籍の場合、いずれにおいても日本国内の財産の相続手続きにあたっては、その外国籍の方にかかる「戸籍に代わる書類」を準備する必要があります。また、海外の財産を相続するにあたっては、その所在地の法律に従った対応が求められることとなります。 (4)日本の相続税と海外の相続税 被相続人、または、相続人が外国籍である場合、相続税については日本の相続税と海外(国籍の国や財産の所在地)の相続税の両方が課税されることがあり、両国の税制や租税条約を確認する必要があります。 なお、被相続人が外国籍の場合も日本の相続税を計算する上での「法定相続人の数」や、「法定相続分」は日本の民法に基づいて判断することとなります。 2-4 海外専門家(弁護士等)との連携 これまで説明してきた通り、国際相続には海外の専門家との連携が不可欠と言えるでしょう。 また、以下のようなケースで日本国内と海外の専門家がそれぞれの持つ情報を共有し合うというのもとても大事です。 【情報共有が重要となるケース】 ・日本にある財産の相続手続きのために日本の弁護士等が収集した戸籍等の情報を、海外の財産の相続手続きのために現地の弁護士に共有する ・海外に所在する財産について現地の税理士・会計士が行った相続税申告の情報を、日本の相続税申告で外国税額控除の適用を受けるために日本の税理士に共有する ポイントとしては、まずメインの担当となる日本で国際相続手続きに精通する専門家(国際弁護士や税理士)を選定し、その方を起点として国内外の専門家を選定し、専門家同士のスムーズな情報共有を図ることが重要です。 専門家が情報をスムーズに共有できれば、二度手間が減り、相続手続きを最短で進めることができます。 逆に言えば、情報共有がうまくいかないと相続手続きにより多くの時間を要することとなります。 想像していたよりも倍以上の期間がかかってしまった、、、というのはよくあるケースです。 第3章 国際相続における税金の仕組み 国際相続においてよく大きな問題になるのが税金です。複数の国の税制度が絡み合い、発生した税金には申告と納税の期限があるためです。国際相続に関する税金の概要について確認をしていきます。 3-1 日本の相続税と海外の相続税(遺産税)の違い (1)相続税(遺産税)制度がある国とない国 まず、相続税(遺産税)の制度がある国とない国があります。 実態として、相続税(遺産税)がない国も多数あります。 (2) 遺産取得方式(相続税)と遺産税方式(遺産税)について 「人が亡くなったことを起因として生じる財産の移転」について税金がかかる場合、その制度は大きく「遺産取得方式(相続税)」と「遺産税方式(遺産税)」という2つの方法があります。 例外はありますが、両者の違いで最も大きいのはプロベート手続きが必要かどうか、という点です。 3-2 二重課税が発生する仕組み このように相続税(遺産税)のルールは各国で定めているため、海外にある財産に対して日本の相続税と海外の相続税の両方がかかってしまう「二重課税」の問題が生じることがあります。 【例】 ドイツに住んでいるドイツ国籍の人が、ドイツに3億円の預金、日本に2億円の不動産がある状態で亡くなった場合 ドイツの相続税→その全ての財産5億円(ドイツにある3億円と日本にある2億円)が対象 日本の相続税→日本にある財産2億円については日本の相続税の対象 さらに、相続人が日本に住んでいる場合は、原則的に日本においても全ての財産5億円が日本の相続税の対象 このように、各国の税金が二重でかかってしまうことを「二重課税」といい、これを防ぐために「外国税額控除」という方法があります。 3-3 外国税額控除の活用 「外国税額控除」とは、簡単に言うと、「海外でも日本でも税金を払うことになったとき、日本の税金から海外で払った分を引ける制度」です。 海外の財産にその所在する国の相続税がかかった場合には、その税額を日本の相続税から控除することができる、ということになります。 具体例を示すと以下のようになります。 【例】 前提:日本に住んでいる方が、日本に7億円の財産、海外に3億円の財産がある状態で亡くなった。相続人は日本に住んでいる子ども1人。 日本の相続税:全世界の財産(10億円)に対して日本の相続税4億円が発生 海外の相続税:海外にある財産(3億円)に対して財産所在国の相続税1億円が発生 この場合、全世界の財産にかかる日本の相続税4億円から、外国税額控除によって海外の財産にかかる海外の相続税1億円を差し引き、残りの3億円だけを納めることとなります。 一方、日本の財産に海外の相続税がかかった場合には、その税額を日本の相続税から控除することができません。したがってその場合には、海外の相続税額からその国の外国税額控除のルールに基づいて日本の相続税額を控除できるかを検討することとなります。 日本の相続税申告で外国税額控除の適用を受ける場合、その控除額は以下のいずれか少ない金額となります。 ・海外で支払った相続税相当額(上記例の場合は海外の相続税1億円) ・日本で支払う相続税のうち海外財産が占める割合分の金額(上記例の場合は、日本の相続税4億円×海外財産3億円/全世界財産10億円=1.2億円) この「外国税額控除」の適用を怠ると、税金を2重で払ったままとなってしまうため、忘れずに適用を受けることが大切です。 第4章 国際相続を円滑に進めるためのポイント 国際相続は日本国内の相続に比べて複雑で、その手続きに多くの負担を要します。 次にその対策について見ていきましょう。 全ての対策に共通しているのは「生前から準備をしておくことが大切」ということです。 4-1 生前からの準備が大切(財産の移動・生前贈与・リビングトラスト・共同所有) 国際相続においてとても負担になるのが海外の相続税(遺産税)とプロベート手続きです。 この負担を軽減する具体策について確認します。 (1)財産を日本へ移す 海外のプロベート手続きを回避するために特に有効な手段は、財産をプロベート手続きがない国へ移すことです。 また、財産を国外に移すことは相続税(遺産税)の対策になることもあります。 例えば、被相続人(亡くなった人)がアメリカ非居住者である場合、アメリカの相続税(遺産税)の対象となるのはアメリカ国内の財産のみとなります。 したがって、アメリカ非居住者がアメリカにある財産を全て日本に移せばアメリカの相続税(遺産税)の心配はなくなることとなります。 (2)生前贈与 例えば、アメリカ非居住者がアメリカにある預金(無形資産)を贈与した場合、アメリカの贈与税はかからないこととなっています。 しかし、贈与者が日本人で日本在住である場合等一定の場合には日本の贈与税が発生することとなるので、この点については留意が必要です。 また、贈与したアメリカの財産はご本人の財産でなくなりますので、将来のプロベート手続きの心配はいらないこととなります。 (3)トラスト(信託)やジョイント(共同所有)の活用 海外にある財産をトラスト(信託)やジョイント(共同所有)にすることは、プロベート手続きを回避する有効な手段となります。 トラスト(信託)とは、財産を所有している人が信託契約によって信頼できる第三者に持っている財産の運用や管理、最終的な処分までを任せるものです。その契約において自分が死亡した時はこの人に財産を渡す、ということを定めておけばプロベートを経ずに財産を移転することができます。 また、ジョイント(共同所有)とは、財産を共同所有にすることです。共同所有者が亡くなった場合にその所有権が残りの共同所有者に移転するため、プロベート手続きが不要となります。代表的なものとしてジョイント・アカウント(共同名義の預金口座)とジョイント・テナンシー(不動産の共同所有)があります。 4-2 日本と海外の専門家チームを組む重要性 これまで説明してきた通り、国際相続には海外の専門家との連携が不可欠と言えるでしょう。 相続人が海外の専門家と直接やり取りをしようとした場合、言語の壁や専門性の高さから多くの負担が生じることとなります。 海外の専門家と連携を図る上でのポイントは、メインの担当として相続人の窓口となる日本の専門家(国際弁護士や税理士)を選定することです。 そして、その日本の専門家を起点として国内外の専門家を選定し、手続きを進めることが重要です。 こうすることで実際の相続手続きにおいて専門家同士のスムーズな情報共有が可能となり、不透明なことが無くなる上、無駄なく最短で手続きを進めることができるでしょう。 4-3 「国際相続に強い」税理士に相談するメリット 国際相続において最も大きな問題となり得るのが日本と海外の相続税(遺産税)です。 海外の税制や二重課税の対処など専門性の高い分野となるため、税理士の中でも「国際相続に強い」税理士に相談することがとても大事です。 また、上記のとおり、メインの担当として相続人の窓口となる日本の専門家に税理士を選定することもメリットが大きいです。 相続税(遺産税)の計算に必要となる情報には、国内外の相続の手続きに必要となる情報が多く含まれています。 したがって、日本の税理士を起点として国内外の専門家に依頼をしやり取りを進めていくことにより、よりスムーズな相続手続きが可能となります。 第5章 国際相続の相談は「税理士法人マインライフ」へ 財産が海外にあり相続の手続きが複雑になるかもしれない・・・。 そのような難しいケースでも、弊社には最適なサポート体制が整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「海外が絡む相続で相続手続きをどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第6章 まとめ いかがでしたでしょうか。 国際相続は日本国内の相続と異なる点が多々ありますが、そのポイントは以下の通りです。 ・国際相続とは、一言で言うと「国をまたぐ相続」 ・国際相続は「法律」と「税金」の両面で複数の国のルールが絡み合うのが最大の特徴 ・国際相続となる典型的なケースは以下の3つ 〇日本国籍の相続人(財産を相続する人)が海外に住んでいる 〇日本に住んでいた被相続人(亡くなった人)が海外に財産を持っている 〇被相続人が外国籍(日本在住)、または、外国籍(日本在住)の相続人がいる ・それぞれのケースによって相続手続きの進め方や必要となる書類が異なる ・海外にある財産の相続についてプロベート手続きが必要となる場合、相当の時間(通常半年~数年)と費用を要することになる ・日本の相続税と海外の相続税(遺産税)には多くの違いがあり、複数国での二重課税を防ぐため外国税額控除の適用が重要 ・国際相続の対策は「生前から準備をしておくこと」が何よりも大切 ・国際相続は日本の税理士を起点として国内外の専門家を選定し手続きを進めるのが最もスムーズ ・国際相続の手続きに不安を感じたら「税理士法人マインライフ」へ! 国際相続は複数の法律や言語が絡み合いとても複雑なものになります。 スムーズな相続を実現するには生前からの準備・対策を行うことが不可欠です。 相続対策は早く始めれば始めるほど、大きな効果を生みます。 将来の相続に備えて、今できることをひとつずつ着実に行っていきましょう!
